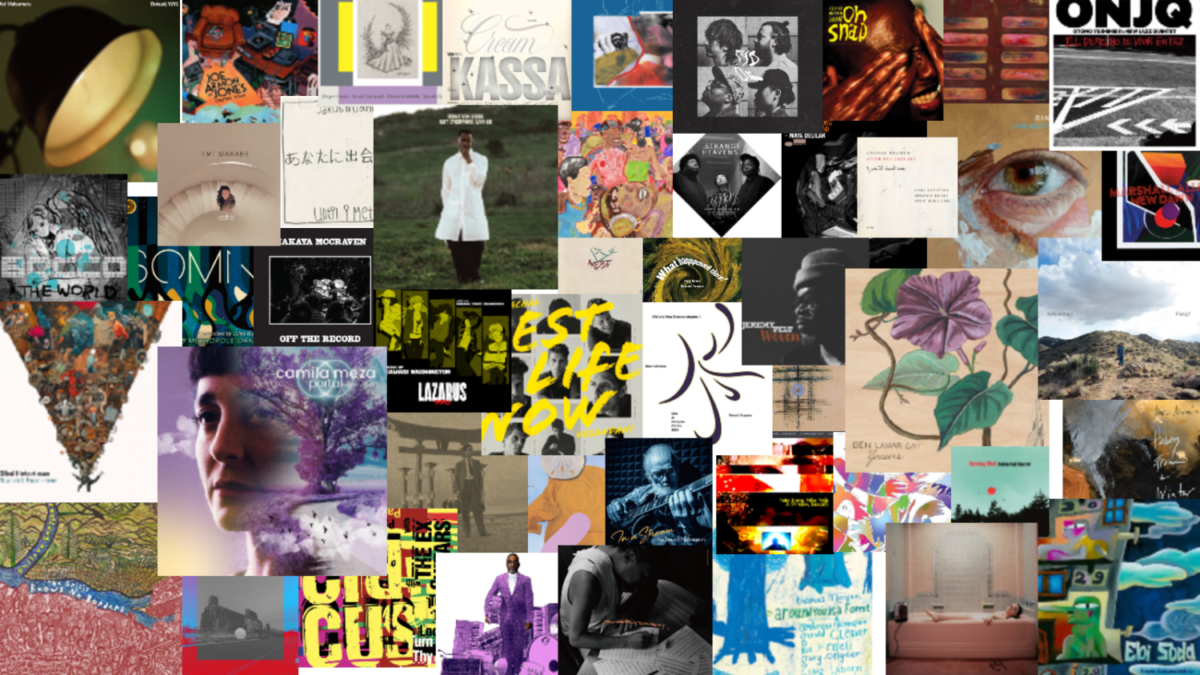2025年にリリースされた ジャズ 作品の中から、聴き逃せない50作をセレクト
選盤・文/土佐有明
Ambrose Akinmusire /Honey From A Winter Stone
Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland /After The Last Sky
Ben LaMar Gay /Yowzers
BOCCO /The World
Braxton Cook /Not Everyone Can Go
Camila Meza /Portal
Cecile McLorin Salvant /Oh Snap
グラミー賞を三度受賞しているヴォーカリストが、名門ノンサッチからリリースしたアルバム。これまでとは制作方法を変え、自らDAWによってひとり宅録で作品を創り上げたそうだが、こぢんまりした印象はまるでなし。いつも通りコケティッシュでチャーミングな歌声を中心に心が浮き立つようなサウンドを築き上げている。あっぱれだ。ジャズからクラシック、ソウルまでを含み、松尾芭蕉の俳句に触発されたという曲もあったりするのが面白い。
Dan Weiss /Unclassified Affections
Donny McCaslin /Lullaby for the Lost
Ebi Soda /Frank Dean And Andrew
Emi Makabe /Echo
Emma-Jean Thackray /Weirdo
藤井郷子カルテット /Burning Wick
Gilad Hekselman /Downhill From Hill
GUSTAVO CORTIÑAS /The Crisis Knows No Borders
謝明諺 /Punctum Visus –視覚 –
井上銘 /Tokyo Quartet
Jakob Bro & Midori Takada /あなたに出会うまで
James Brandon Lewis /Apple Cores
Jamie Leeming /Sequent
Jeremy Pelt /Woven
Joe Armon-Jones /Starting Today
Joshua Redman /Words Fall Short
Kamasi Washington /Lazarus (Adult Swim Original Series Soundtrack)
Kassa Overall /CREAM
Kokoroko /Tuff Times Never Last
黒田卓也 /EVERYDAY
桑原あい /Flying?
Linda May Oh /Strange Heavens
Makaya McCraven /Off The Record
Mark De Clive-Lowe /Past Present (Tone Poems Across Time)
Marshall Allen /New Down
Mary Halvorson /About Ghosts
松丸契 /Dokusō, YūYū
Maya Delilah /The Long Way Round
中牟礼貞則 /In a Stream
Nate Smith /Live-Action
Nels Cline /Consentrik Quartet
Old and New Dreams chapter.1 /序
大友良英ニュー・ジャズ・クインテット /El Derecho de Vivir en Paz
Paal Nilssen –Love Circus with The Ex Guitars /Turn Thy Loose
Peter Evans, Mike Pride /A Window, Basically
Sachal Vasandani /Best Life Now
SML /How You Been
Snarky Puppy & Metropole Orkestra /Omni
Sun –Mi Hong /Four Page Meaning Of A Nest
田村夏樹 &灰野敬二 /What happened there?
Thomas Morgan /Around You Is A Forest
Tom Skinner /Kaleidoscopic Visions
44th Move /Anthem