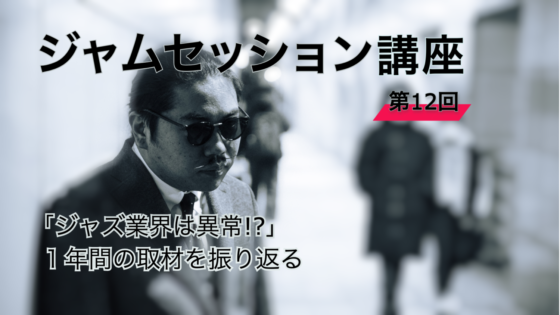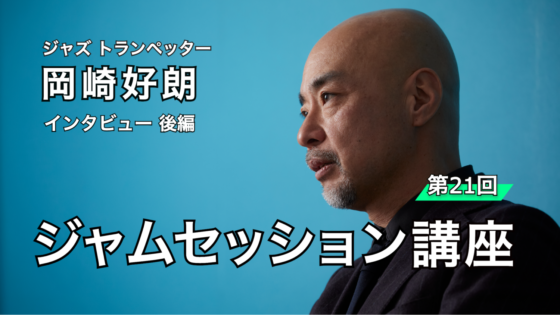投稿日 : 2025.11.14
なぜ秋はジャズフェスティバルが多いのか? 運営費、世代交代、開催意義、そして魅力を主催者たちに聞く【ジャムセッション講座/第36回】

MENU
今回は秋に全国各地で開催されるご当地ジャズフェスの運営の裏側などを、「神戸ジャズストリート」「すみだストリートジャズフェスティバル」「阿佐ヶ谷ジャズストリート」の主催者たちに聞いた。
【担当記者】
千駄木雄大(せんだぎ ゆうだい)
ライター。32歳。大学時代に軽音楽サークルに所属。基本的なコードとパワーコードしか弾けない。セッションに参加して立派に演奏できるようになるまで、この連載を終えることができないという苦行とともに執筆中。「最近の悩みはなんですか?」と聞かれたものの、「食いしばり」「ドライアイ」「肩こり」と身体の不調しか思い浮かばなかった。
秋に集中するジャズフェス
かつてジャズ・フェスティバルは夏の風物詩だったが、最近は秋から初冬にかけて盛んに実施されているらしい。ロックフェスは若者が中心だから真夏でもOKだけど、ジャズは年齢層が高いから気候が穏やかなに移行した、ってことなのか? 当サイト『ARBAN』の「ジャズフェスカレンダー」を見ても、9月以降の開催数がものすごく多い。しかも日本全国さまざまな“ジャズフェス”が開催されていて、地域のコミュニティや自治体と結びついたジャズイベントが盛りだくさん。
そうした “ご当地フェス” には有名アーティストも出演するが、主役は市民バンド、つまりアマチュアだ。しかも当連載のテーマである「ジャムセッション」も行われているらしい。つまり、ご当地ジャズフェスは筆者の活動拠点にもなりうるのだ。が、その実態が謎すぎる。一体、これらのフェスを支えているのは誰なのか? そもそも、なぜ「ジャズ」なのか?
その疑問を解くために、兵庫「神戸ジャズストリート」と、東京「すみだストリートジャズフェスティバル」「阿佐ヶ谷ジャズストリート」の主催者たちに話を聞いた。
元祖“アマチュア主導”のジャズフェス
兵庫県神戸市中央区のさまざまな施設で行われる「神戸ジャズストリート」は、一部無料エリアもある有料イベントだ。1982年、ラジオ関西のプロデューサーだった末廣光夫氏が三宮駅周辺で始めたこのフェスは、今年で42回目を迎える。
当時をよく知る神戸ジャズストリート実行委員会・実行委員長の田中千秋氏はこう語る。
「末廣さんはラジオ関西で “プロデューサー”という肩書きでディスクジョッキーをしていました。電話リクエスト形式を広めて、スウィングやディキシーなど、さまざまなジャズを届けてくれたんです。そして、まだライブをやっていなかった『ジャズライブ&レストラン ソネ』の2階にある小さな部屋を事務所代わりにして、ジャズストリートの運営を始めました」
今では、サブスクリプションやYouTubeで気軽にジャズを楽しめる時代だが、当時はそうではなかった。だからこそ、街なかで生のジャズを聴けるこのイベントは、多くの人にとって新鮮だった。
「80年代、ジャズは高級クラブで聴くものでした。僕は81歳になりますが、子どものころにはジャズ喫茶がたくさんあったものの、大人になる頃にはすっかり減っていました。だから、街中のさまざまな場所でジャズが演奏されるイベントは、世間から好意を持って受け入れられたんです」(同)

初期はアマチュアミュージシャンが中心だったが、いつしかオランダなどヨーロッパからプロを招くようにもなった。
「ただ、正式に招聘するとギャラが何百万円もかかる。そこで、観光で来日してもらい、会場で“即興”で演奏してもらったのです(笑)。でも、当時は外国人ミュージシャンの生演奏なんて、そうそう見られませんでしたからね。いまでも採用している“ジャムセッション形式”は、そんな流れから生まれたものです。例えば、会場にピアノ・ベース・ドラムのトリオがいて、そこにサックスやトランペットが飛び入りで加わるという形です。誰でも参加できるわけではなく、演奏力のある者たちが “戦いを挑むように”入れ替わり立ち替わりジャムセッションを繰り広げる……。これも魅力のひとつです」(同)
神戸ジャズストリートは、近畿圏だけでなく全国に “アマチュア主導” のジャズフェスを広げるきっかけにもなったという。
「本音を言えば、プロを呼ぶ余裕がなかったんです。でも、当時のアマチュアは今とは違い、誰でもなれるものではなかった。実力派が多かったので、十分に楽しめる演奏になりました」
運営費はチケット収入に加え、神戸市文化振興財団を通じた協賛金が支えとなっている。また、神戸電力、介護付き有料老人ホーム「サンシティタワー神戸」、トーカロなど、地域企業からの協力も厚い。
こうして42回も続いてきた背景には、創設者・末廣氏のカリスマ性がある。2012年に亡くなるまで、彼の存在がイベントの “推進力” だった。
「ただ、僕のようにジャズに夢中だった実行委員会の若者たちも、今ではすっかりおじいちゃんとおばあちゃんです。そこで、4年前から中西幸宏くんという若い世代に、実行委員として入ってもらいました」
中西氏は、もともと神戸ジャズストリートのホームページ制作に携わっていた企業の営業担当。田中氏とは50歳の年齢差がある。
「演者も観客も高齢化が進んでいる今、若い人がもっと気軽に関われるような仕掛けを、これからは積極的に考えていきたいと思っています。でも、これまで支えてくれたプレイヤーたちへの感謝は変わりません。彼らを大切にしながら、新しい風も取り入れていきたいんです」
コロナ前の盛り上がりを取り戻したい
80年代から続く老舗だけでなく、近年誕生したジャズフェスも多い。
「街が音楽でにぎわい、みんなでひとつのことをやり遂げて、終わった後には打ち上げで盛り上がる……。創始者たちは、そんな喜びや達成感を分かち合える場をつくりたいと思ったんです。そのきっかけとなる音楽が、“ジャズだったらカッコいい” という理由で、すみだストリートジャズフェスティバルは始まりました」
そう語るのは、すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会・実行委員長の多賀健太郎氏。もともとは出演者として参加していたが、次第にボランティアとして関わるようになり、いつの間にか運営側に回っていった。

すみだストリートジャズフェスティバルは2010年に始まり、今年で15周年。全会場が入場無料で、出演者は「一般バンド」と「招聘バンド」に分かれている。
「墨田区は1980年代に “音楽都市宣言” を掲げていて、その後、1990年代になってJR錦糸町駅近くに『すみだトリフォニーホール』というクラシックホールが完成しました。今も多くのコンサートが開かれており、文化や芸術への取り組みが活発なんです。1985年に両国国技館ができたときには、5000人で『第九』を歌うというイベントも開催され、それが今でも続いています」(同)
こうした文化的な土壌のある墨田区が後援につき、行政と連携しながらボランティアによってフェスは運営されている。やおきんやアサヒビールなど地元企業の協賛を得て、地域が一体となってイベントを支えている。
ただし、コロナ禍以降、フェスは元の形には戻れていない。
「2019年は規模も参加バンド数も過去最大でしたが、翌年はコロナ禍で無観客・オンライン配信に切り替えざるを得ませんでした。2022年、2023年に再開はしたものの、協賛企業が減ったり、協力してくれていたお店が閉店してしまったりと、運営は厳しい状況です。その影響で、その2年間は赤字となってしまいました」(同)
その赤字はどう乗り越えたのか?
「すみだジャズは任意団体なので、役員で最終的な収支責任を負うとはいえ、資金面はかなり綱渡りです。さまざまな予算を切り詰めて、雨天対策費という開催時の保険のような項目を切り崩してきました。そして、それを使い切ったのが2年前です」(同)
すみだジャズ立て直し策として、一般的に「フェス飯」として注目されるイベント飲食コンテンツに注目し、オクトーバーフェストとジビエフェスティバルを同時開催しているかのように見せるアイデアを思いつき、ジャズフェスを含めた3イベントを同時に楽しめるような演出をしている。
また、墨田区在住在勤の多賀氏が3代目実行委員長に就任し、すみだジャズのポリシーを引き継ぎながら、地域との結びつきをさらに強化して、地に足を着けた健全な運営に取り組んでいる。
「みんなが面白いと思うこと」を企画して、それをボランティアがやりがいを感じながら実行していく、地域に根差した団体であること、それが今後のすみだジャズ継続には欠かせないと感じているという。
かつては全体予算が3000万円近くにのぼる年もあったが、国や都、墨田区からの助成金に頼らず、自主運営を貫いている。全会場無料のイベントであるため、収入源はTシャツなどのグッズ販売の売り上げ、オクトーバーフェストとジビエフェスティバルの出店料、そして地元企業を中心とした企業や団体の協賛金、イベント当日に来場者から応援の気持ちを込めた募金だ。
再び活気を取り戻そうと奮闘する多賀氏は、東京の下町エリアで開催するジャズフェスティバルに込めた思いをこう語る。
「日本のジャズって、ちょっと敷居が高く感じる人も多いと思うんです。ジャズバーは値段も高めだし、雰囲気も少し格式がある。でも、下町にはもっとゆるやかで、誰でも受け入れる空気があります。そんな街に、年に2日だけ “ジャズが自由に楽しめる空間” が現れる。それがすごく面白いんです」

本格派のジャズミュージシャンによる演奏もあれば、かつてバンドを組んでいた “お父さんバンド” が楽しそうに演奏する姿もある。観客のおばあちゃんが「音楽っていいね」と微笑む……。そんな光景こそが、“すみだらしさ” だと多賀氏は言う。
「ジャズフェスといっても、そこまで “ジャズ” にこだわっているわけじゃないんです。この “ゆるさ” こそが、すみだジャズの魅力なのかなと思います」
民間企業がジャズフェスを運営する使命感
このように、多くのジャズフェスティバルは市町村が主催するのではなく、後援に回るかたちをとっている。運営の中心は、ボランティアで構成された実行委員会だ。
「出身は千葉県船橋市で、阿佐谷に住み始めて10年になります。ジャズに特別詳しいわけではありませんが、5年前にホームページのリニューアルを担当したことをきっかけに、阿佐谷ジャズストリートの実行委員会に加わるようになりました」
そう話すのは、阿佐谷ジャズストリート実行委員会の事務局長・柴田真光氏。グラフィックデザインなどを手がける「ネイバーズグッド株式会社」の代表取締役でもある。
阿佐谷ジャズストリートは1995年にスタートし、今年で30回目を迎える。会場は駅前のステージだけでなく、小学校、教会、区役所、ストリートなど、約60カ所にのぼる。中でも注目は、阿佐ヶ谷神明宮の能楽殿で行われる、山下洋輔氏によるライブだ。
無料で楽しめるストリート会場から、著名ミュージシャンも出演する有料会場に分かれている。山下氏のステージは有料で、前売券が4000円、当日券は5000円。ほかにも1000〜2000円の有料会場がある。
「1995年といえば、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件が起きた年です。当時、阿佐谷にもオウム真理教の道場があり、街全体にどこか暗い空気が漂っていました。そうした状況のなか、杉並区民や商店街、町会の方々が『ジャズで街を元気に!』というコンセプトを掲げて立ち上がり、行政を巻き込んで始まったのが、阿佐谷ジャズストリートなのです」
以来、地元のジャズバーのマスターなどが実行委員を務めながら活動を続けてきた。しかし、30年が経ち、中心メンバーの平均年齢は70代に。次世代へのバトンタッチが求められ、柴田氏がその役割を引き継いだ。
「以前は、会場を自由に回れる “パスポート” は紙チケットでしたが、コロナ禍以降はオンラインチケットに移行しました。つまり、急速にデジタル対応が求められたのです。かつてのメンバーは、その対応になせる術を持ち合わせておらず、困り果てていました」
コロナ以降、多くのイベントが中止や縮小に追い込まれた。背景には感染症対策だけでなく、別の課題もある。
「ひとつは消防関連の規制です。これはコロナとは直接関係ありませんが、以前よりもかなり厳しくなりました。ライブハウスのような常設の興行施設であれば問題ありませんが、ジャズストリートの会場は学校や教会、区立施設など、本来演奏を目的としない場所が多いため、毎回、消防への申請が必要になります。“何人収容できるか” “火災時にどのように避難できるか” といった避難シミュレーションを作成・提出しなければならないのです」
これを数十か所分、毎年準備しなければならないのは、大きな負担だ。しかも、柴田氏はデザイン会社の経営という本業と並行して、非営利組織の運営に携わっている。
「それに運営費はチケット代と広告協賛が中心です。一部補助金もいただいていますが、基本はチケット収入が柱。それでも、黒字になることはほとんどありません。“非営利だから赤字でいい” というわけではなく、結果的に毎年ギリギリの収支なんです」
それでも柴田氏が実行委員を続ける理由とは? まさか年配の委員たちに無理やり押しつけられたのでは……?
「いえ、それが “使命” だと感じているんです。うちの会社は “街を舞台にした事業” を数多く手がけています。地域の人たちを主役にするという考えが根底にあって、助け合いによって地域社会を育てることが、会社のビジョンでもあります。その象徴的な取り組みのひとつが、このジャズストリート。『阿佐谷でジャズストリートをやっています』と言えば、誰もが知っていて、ビジョンの代名詞でもあり、模範としても捉えさせてもらっています。だからこそ、この活動を続けることが、僕自身の使命であり、会社の理念そのものなんです」
世代を超え、立場を超えて、さまざまな人たちが力を合わせ、ジャズフェスの運営に取り組んでいる。もっと多くの人にジャズを届けたいという、静かで熱い想いがそこにはある。
その集大成ともいえる、地域で開催されるジャズフェスティバル。近くで開催されるフェスがあれば、ぜひ足を運んでみてほしい。
構成・文/千駄木雄大
ライター千駄木が今回の取材で学んだこと
- 秋冬はどこかしらでジャズフェスが行われる
- フェス運営の世代交代は大きな課題
- 運営費は自分たちで賄う
- ボランティアの協力は必須
- “地元を盛り上げる音楽フェス” って素敵