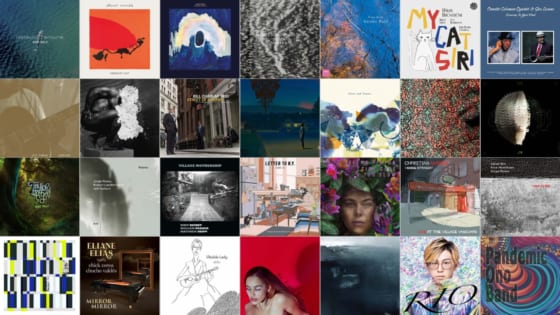投稿日 : 2020.01.01 更新日 : 2022.04.19
【江﨑文武 インタビュー】ジャンルを横断するのは当然。「今いる場所から逃れようとする力=ジャズ」なのだから
取材・文/村尾泰郎 撮影/高瀬竜弥

MENU
「エクスペリメンタル・ソウル」というキーワードを掲げ、ジャズ、R&B、ヒップホップを独自にブレンドしたサウンドで注目を集めるバンド、WONK。そこでキーボードを担当する江﨑文武は、King Gnuなど様々なアーティストとの作品に参加。映画やCMの音楽を手掛けたり、石若駿と『JAZZ SUMMIT TOKYO』というプロジェクトを立ち上げて同世代(90年代生まれ)ジャズ・ミュージシャンの交流の場を設けるなど幅広い分野で活動してきた。
中学でビル・エヴァンスの音楽に出会ったことから始まった江﨑の音楽発見の旅。ジャンルを横断することの重要さや、同世代の仲間たちとのクリエイティヴな交流について話を訊いた。
中学生でビル・エヴァンスに挑戦
ーー江﨑さんは中学生の頃に、ビル・エヴァンスの音楽に出会ってジャズを聴くようになったそうですね。
YAMAHA音楽教室でピアノを習っていたんです。そこで出会った同い年の男の子が、実はドラムやパーカッションもやっていて。その子に「ジュニア・オーケストラで打楽器をやってるんだけど遊びに来ない?」と誘われたんです。入ってみたらコントラバスの友達ができた。そうするとピアノ・トリオができるじゃないですか。そのタイミングで、親父が買ってきた『ワルツ・フォー・デビィ』を聴いて衝撃を受けたんです。ビル・エヴァンスのコピーを始めたのは、あのアルバムの影響が大きい。

ーー中学生でビル・エヴァンスに挑戦したんですか!
〈マイ・フーリッシュ・ハート〉の完コピを3人でやるというのが最初のバンド経験でした(笑)。『ワルツ・フォー・デビィ』のライナーノーツに「シンバルの先まで美しい」って書いてあったんですけど、響きの美しさが衝撃的で自分たちでもやってみたいと思ったんです。そこから、マイルス・デイヴィス、チック・コリア、キース・ジャレットと聴いてECMに辿り着いたんです。
藝大の面接は iPadでプレゼン
ーーそのまま音楽に夢中になって東京藝大に?
もともとモノ作りが好きで、本当は工学部に行きたかったんです。でも、先の流れで一緒にトリオをやっていたドラムの子が「バークリーに行く!」と言い出して、コントラバスの子は藝大に。そんな二人の影響で、僕も音楽大学や藝大を受験してみようかなと思ったんです。
ーー学部はどこを?
藝大の中では新設学科である、音楽学部の音楽環境創造科というところです。コンピュータープログラミングによる作曲や音響、アートマネジメントなど、これまでの藝大にはなかった領域を教える学科。そのなかに、コンピュータを使った音楽制作を教えてくれるゼミがあって、僕はコンピュータや映画音楽、録音音響に興味があったので、そこで学びたいと思ったんです。
受験の面接時、教授から「藝大で何をしたいか言ってごらん」と訊かれて、僕は「もっとテクノロジーに目を向けた上で、日本の音楽の諸要素を取り入れたものをやるべきだ」という、すごく生意気で何もわかっちゃいないプレゼンをしたんですよ(笑)。「これからは楽譜やコンサートホールではなく、手のひらサイズのコンピューターで音楽を作り、聴くことまでが完結する時代だ」と思っていたので、当時発売されたばかりのiPadを使い、タブレットだけで完結するプレゼンをしました。
ーーなかなか挑発的なプレゼンですね。藝大で印象に残った授業はありました?
いま考えてみると、そこで出会った仲間から学んだものが一番大きかったですね。あと、藝大は美術学部が併設されているので、そちらの授業も取れるんです。
なかでも建築科の授業がめちゃくちゃ面白くて、「建築家がものを作るときに考える概念が、どこから由来したものなのか?」を領域横断的に教えてくれた授業は印象に残っています。例えば、同じパーツを組み合わせて大きな組織を作った、黒川紀章の『中銀カプセルタワー』は、メタボリズムという概念を元に設計されているんですけど、それは「エリック・サティのヴェクサシオンで萌芽し派生した、ミニマル・ミュージックの概念に通じるものがある」とか。そんな風に他学部との交流が簡単にできるのが藝大の良さでしたね。

早稲田ジャズ研で過ごした濃密な時間
ーー音楽活動はどうしていたんですか?
「入学したらいろいろな形で楽団やバンドを組んだりできるかもな」と思っていたんです。でも、純粋にクラシックをやっている人が多かったのと、僕が通っていた学科は演奏家がいなかったこともあって、そんな雰囲気はなかった。ただ、石若駿の名前だけは高校の時から雑誌を通じて知っていました。「ヤバい同い年がいるぞ」って。でも、学科が違うので一緒に演奏する機会はそう多くなくて…。そこで長い歴史を持つ早稲田大学のジャズ研に行ってみたら、いろんな出会いがあったんです。藝大より(早大)ジャズ研にいた時間のほうが長かったかもしれないですね。
ーープレイヤーとしての感性は早稲田で磨かれた?
そうですね。とにかく刺激的でした。部室に行くと常に誰かがセッションしているんです。そこで交わされる音楽の話も面白くて情報量も全然違う。当時はロバート・グラスパーの話題が多かったかな。そこでWONKのリーダーの荒田(洸)と出会ったんです。ジャズ研に出入りしている人はファッションに興味のない人が多かったんですけど、荒田はキャップをかぶってヒゲをはやして、出で立ちがまわりと全然違った。一緒にセッションしてみると、「この人とは展開のヴィジョンが重なるな」と思えたんです。それと、あんなにクリス・デイヴっぽいヤツはジャズ研にはいなかった(笑)。

ーーそして、荒田さんからWONKに誘われるんですよね。当初は「J・ディラ系譜のビート・ミュージックをやる」というコンセプトがあったとか。
誘われたのは大学3年の頃だったと思います。メッセンジャーに「バンドやらない?」と連絡がきて、すぐに「やる」と返しました。でも、J・ディラは全然聴いていなかったんですよ。当時はECMが好きで、必死に生活費をやりくりして数万円出してキース・ジャレットのコンサートに行くような感じだったので。でも、荒田からグラスパーも J・ディラから影響を受けていることを教えてもらって、ヒップホップを掘っていた井上(WONKのベースの井上幹)からは、ブルーノート・レコード作品をサンプリングしている曲を教えてもらったり。そういった経緯でヒップホップをいろいろ聴くようになったんです。
固定観念を解放してくれたヒップホップ
ーーヒップホップからはどんな影響を受けました?
「生演奏にはプレイヤーにしか出せないグルーヴがあって、それが美しいことだ」とずっと思っていたんです。「コンピュータで音楽を作る時代だ」と思いながらも、演奏家としての自分は「フィジカルな演奏のカッコよさ」みたいなものを捨てきれなかった。でも、ヒップホップの人たちがグルーヴを生み出すために、波形を(微細に)“髪の毛” 分だけずらすとか、そういう音響的な工夫をいろいろやっていることを知って、「機械ではグルーヴを生み出せない」という固定概念から開放されました。
ーーそういうグルーヴに対する開かれた感覚は、WONKのサウンドに反映されていますね。
めちゃくちゃ反映されていると思います。とくに荒田と井上はソフトで作り込むグルーヴに興味を持っていたので、僕が生で入れた音をうまく成型してくれたり、お互いに学び合える環境がWONKにはあるんです。
ーー江﨑さんが感じるWONKのバンドとしての面白さはどんなところですか?
それぞれ好きなものが違い過ぎて、普通なら一緒にバンドを組まないメンバーなのかもしれません。そこが面白さにつながっているというか(笑)。でも、これだけバックグラウンドが違うからこそ、オリジナリティのあるものができると思っています。好きなものはバラバラだけど、音楽的な協調性はある。「あいつがこれをカッコいいと思っているなら、オレのカッコいいものとうまく混ぜ合わせれば面白いかも」みたいなマインドをみんなが持っていて、お互いに歩み寄る姿勢が強い。
ーーそれは、全員がセッション志向の強いプレイヤーであることも関係あるのでしょうか。
確かに、言われてみるとそうかも。それぞれがセッション・プレイヤーとして、いろいろな人たちといろんな音楽を楽しむことを知っている、というのは大きいと思います。荒田がリーダーなので彼がコンセプト的なものを最初に持ってきますが、曲を作り上げていく過程での関係性は対等で、お互いに助け合えるのがWONKの良いところだと思います。
ジャズの若手はマスに向けた発信ができていない
ーーWONKは自分達のサウンドを説明する時、「エクスペリメンタル・ソウル」という言葉を使っていますが。ジャズ、ヒップホップ、R&Bなど、いろんな要素が混ざり合っているのがWONKの特徴ですよね。
僕らはひとつのジャンルや音楽にこだわっているバンドではないんです。最初こそ「J・ディラ系譜の〜」というコンセプトがありましたが、最近はそれも言っていなくて。自分たちが面白いと思うもの、「音楽表現を先に進める可能性があるもの」は全部やりたいというスタンスなんです。
ーーそういうジャンルレスな音楽性は、LAのブレインフィーダー周辺のアーティストに通じるところもありますね。
ブレインフィーダーはめちゃくちゃ意識していました。最近だとオーストラリアやイギリスで、ジャズを起点としてポップなサウンドをやるアーティストの交流が盛んになっている。そういう流れも面白いなと思います。
ーーかつて、石若駿さん、中山拓海さん、ぬかたまさしさんたちと『JAZZ SUMMIT TOKYO』というプロジェクトを立ち上げて、同世代のジャズ・アーティストとイベントをやられていました。そこには日本でもそういうシーンを作りたいという想いがあったのでしょうか。
あのプロジェクトを始めたのは、「同世代のメンツ、めちゃくちゃ良いミュージシャン多いぞ!」と思ったからなんです。ただ、音楽的に素晴らしいけれど、発信の仕方はもっと考えたほうが良いと思っていて。ポップスのフィールドだったら新曲をリリースするときはMVを作るし、ライヴのためのティーザーを作ったりするじゃないですか。でも、ジャズの若手はマスに向けた発信ができていないと思ったんです。プロデューサーもどんどんいなくなっている。そういうことの是非を議論できる場として、『JAZZ SUMMIT TOKYO』をやりたかったんですよね。
ーーWONKをはじめ、石若さんやKing Gnuなど、江﨑さんと交流がある同世代のアーティストは、ジャズにこだわらずにいろんな音楽を取り入れています。そういう間口の広さや好奇心の旺盛さは、同世代アーティストに共通するところだと感じますか?
『JAZZ SUMMIT TOKYO』では、「ジャンルを横断することはすごく重要だ」という話をみんなでしていて。「ひとつの音楽ジャンルだけで成立している人間なんているのか?」というのが、みんなの共通認識としてありました。「あれも好きこれも好きというのは、アーティストとしての弱さではないか?」という意見もありましたが、いろんな音楽をコラージュ的に盛り込むことに面白さを感じている世代なのかもしれないです。とくに石若はジャンルを横断することにずっと意欲的だったし、自分もWONKをやるようになってからは、ジャズ以外のジャンルの面白さを知るようになりました。

今いる場所から逃れようとする力がジャズ
ーーそんななかで、ジャズという音楽に対して新しい発見はありましたか?
周囲のアーティストとよく話しているのは、「今いる場所から逃れようとする力がジャズだ」ということです。常に実験的で、前からあった音楽とか、その前に自分がやっていた音楽から逸脱しようとするところに「美」を感じる人たちがジャズ・ミュージシャンなんじゃないか? って。そういうマインドは自分のなかにずっとありますね。ジャズ・ミュージシャンがセッションを好むのは、外的要因によって自分のスタイルを変容させて次のステップに向かうためだと思うんです。
ーー江﨑さんがこれから挑戦してみたいことはありますか?
昔から空間や建築に関心があって。ブライアン・イーノ系譜のアンビエントミュージックの立ち位置を軸に、日本人的な『間』の感覚、そしてこれまでの『自分のバックグラウンド』を結びつけた音楽を表現したいと思っています。日本人は環境の音に敏感で、例えば、歌舞伎で太鼓を優しく叩く音は雨音を表しているんです。そういう空間や環境、自然を音楽的に捉える感覚って、今も僕ら日本人の中に染みついているんじゃないかと思っていて。今後は音楽以外の人とも手を組んで、自分の美学だけで何かを作ってみたいですね。
以前から、30歳になるタイミングで自分らしさを前面に出した作品を作りたいと思っていたんです。タイムリミットまであと3年なので、そろそろ動き出そうかなと思っています。
公式サイト:http://www.wonk.tokyo/