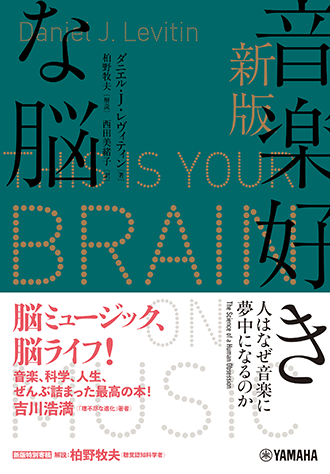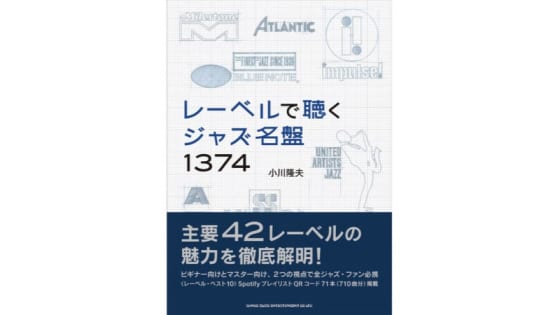投稿日 : 2022.02.28
“ジャズ界の外様” 新聞記者が書いた戦後邦ジャズ史─『秋吉敏子と渡辺貞夫』著者インタビュー
取材・文/二階堂 尚 撮影/高瀬竜弥

読売新聞の文化部で長年ポピュラー音楽に関する記事を執筆してきた西田浩氏。彼が初めて手掛けたジャズ関連書籍が『秋吉敏子と渡辺貞夫』(新潮新書)だ。日本のモダン・ジャズの2人の先駆者の歩みをたどりながら、戦後の日本のジャズの歴史を簡潔にまとめたこの本が書かれた経緯や、音楽本を取り巻く状況について西田氏に聞いた。
世界を目指すモデルをつくった2人の先駆者
──この本のベースとなったのは新聞の連載記事だそうですね。
読売新聞の「時代の証言者」という企画で渡辺貞夫さんを取り上げたのが2011年のことです。貞夫さんに長時間お話を聞いて、一人語りの形式で25回にわたって彼の半生をまとめした。
その後2017年に、ベテランのジャズ・ミュージシャンにインタビューをする連載記事を企画しました。2017年はジャズの最初のレコード発売から100年目の年です。その節目に日本のジャズの歴史を振り返ってみようと思ったわけです。その連載で取り上げたのが、貞夫さん、秋吉敏子さん、原信夫さん、北村英治さん、山下洋輔さん、渡辺香津美さんの6人です。さらにその翌年も秋吉さんにお会いしてじっくりお話を伺う機会がありました。
それらの取材で得た貴重な証言を本にできないかと考えたのが2018年です。以前に出したロックの本の担当編集者に相談したところ、本にするなら貞夫さんと秋吉さんに絞った方がいいという意見でした。そうして、2人のこれまでの歩みをまとめたのがこの本です。

──2人の評伝でありながら、戦後日本のジャズの簡潔な略史にもなっているという構成がこの本の特徴になっています。秋吉さんと貞夫さんのそれぞれの物語が徐々に交差していって大きな流れになっていくところが一つの読みどころだと思います。
2人の歩みが最初に交わったのは、1953年のコージーカルテット結成でした。コージーカルテットは秋吉さんがつくったグループで、そこに貞夫さんが参加したわけです。2人が一緒に活動したのは2年くらいでしたが、あのバンドが日本のモダン・ジャズの一つの出発点となっています。
その後、秋吉さんは56年にバークリー音楽院に留学し、貞夫さんも秋吉さんに呼ばれる形で62年に渡米しました。日本のジャズ・ミュージシャンがアメリカを目指す流れは、そこから生まれています。小曽根真さん、大西順子さん、上原ひろみさん、山中千尋さん──。現在、海外でもよく知られている人たちの多くはバークリー出身ですよね。あの2人が日本のジャズ・ミュージシャンが世界を目指す美しいモデルをつくった。そう言っていいと思います。

──本では、その後の2人の世界での活躍から、ごく最近までの姿までが描かれています。本編の最後にある「昨日より少しでもうまくなりたいと、毎日ピアノに向かう。それは10代で演奏活動を始めてから、まったく変わっていません」という秋吉さんの言葉が印象的でした。
1970年代以降の日本のジャズ史をまとめた本って、実はあまりないんですよね。秋吉さんと貞夫さんは70年代以降も今日までずっと第一線で活躍していますから、そこはしっかりフォローしておかなければならないと考えました。
普通、音楽雑誌などにミュージシャンが取り上げられるのは、新譜を発売したときか、大きなコンサートなどのイベントがあるときです。僕は新聞記者として、それ以外のタイミングでインタビューをさせてもらえる機会が何度もありました。そのときに得られた証言が、最近までの2人の姿を描くのに役立っています。
音楽本を出版することの意味とは
──執筆に当たって最も苦労されたのはどこでしたか。
原稿は一から書いていますが、連載記事という叩き台があったので、執筆自体はそれほど苦労しませんでした。一番たいへんだったのは事実関係の確認です。国立国会図書館に一週間くらい通って、細かなところを調べました。
もう一つあるとすれば、「ジャズ史観」のようなものをどうつくるかという点ですね。僕は文化部の記者として長年ポピュラー音楽について書いてきたのですが、ジャズの専門家ではありません。ジャズ界の外様の身として、どのような切り口でジャズの歴史を語るか。そこはかなり考えました。もっとも、ジャズの専門家ではないからこそ好き勝手に書けるという利点もあります。いろいろ考えた末に、開き直って書くことにしました。
──新聞は専門誌と違って読者ターゲットが広い媒体ですよね。そこで長年記者をされてきた経験による客観的な書き口もこの本も魅力だと思います。
新聞記事には、専門的な知識がない人でもわかるように書くという大原則がありますからね。例えば、「ビバップ」という言葉にも、「アドリブ主体で構成された1940年代のジャズの新しい様式」といった説明を加えなければなりません。ジャズ・ファンからすればまどろっこしい記述ですが、媒体の特性上仕方がありません。
確かに、そのような書き口が僕自身の職業的な習い性になっていると思います。その習い性のゆえに文章がわかりやすいという面があるかもしれませんが、それも良し悪しですね。ロックの本を書いたときは、編集者から「もっと自分を出してもいい」と言われましたし、インターネットの評価などでも「温度が低い」と書かれたりしました(笑)。いずれにしても「俺はこの音楽を崇拝する!」みたいな熱狂的な文章は書けませんから、自分の書き口で書くしかないと思っています。

──音楽本を読んでもらうことの難しさをどう感じていますか。
音楽ファンは必ずしも活字のファンではないというのは確かですね。これまで何冊か音楽関連本を書いてきましたが、さしたる実績もないのによく出してもらえたものです(笑)。
──海外だと、2段組みで600ページを超えるような分厚いミュージシャンの評伝本がよく書かれています。ああいったスタイルは日本の音楽本にはほとんどありませんよね。
あのような本を書くのは、アーティスト・サイドの全面的な協力がないと難しいでしょうね。欧米では、評伝や自伝が出版されるのはひとかどの人物になった証明でもあるので、本を出したいと考えるミュージシャンが少なくないのだと思います。日本にはそういう意識があるミュージシャンがまだあまりいないということかもしれません。
──本が売れないと言われる中で、音楽本を出すことにはどのような意味があると思われますか。
記録性だと思います。書籍として発売されれば基本的に国立国会図書館の蔵書に入ります。今書いた本が100年後、200年後にも参照されるような資料になるわけです。このことの意義は大きいですよね。最近、小川隆夫さんが出された『マイルス・デイヴィス大事典』のような本などは、マイルスと直接の接点があった書き手による一級の資料と言っていいと思います。もちろん、自分が書いた本は売れてほしいですが、それほど売れなくても資料としての価値はある。そう自分に言い聞かせています(笑)。
フュージョンをジャズの正史に位置づけたい
──「ロックな言葉」「日本ジャズの断面」と、読売新聞オンラインで連載を続けていらっしゃいます。これらの連載もいずれ本になるのでしょうか。
「ロックな言葉」は本にできるかなと思ったこともありましたが、難しかったですね。音楽本の中でも、とくにオムニバス形式の本は売れないのだそうです。「ロックな言葉」は、毎回有名なロック・ミュージシャンの発言を取り上げたコラムだったのですが、1回ごとに完結する文章なので、それを集めて一冊にしても売れない。本にするなら全体でストーリーのあるものにしないといけない。そう編集者から言われました。まあ、いずれの連載も、今後本にしていただける機会があればぜひ、という感じですね。
──これから取り組んでみたいテーマはありますか。
興味があるテーマはフュージョンです。1960年代生まれの僕の世代にとって、フュージョンは青春の音楽です。しかし、ウィントン・マルサリスの登場以降、フュージョンはジャズの鬼子と捉えられるようになってしまいました。
僕は、フュージョンはジャズの歴史における一種のルネッサンスだったと思っています。新しいテクノロジーがあるなら、それを使って新しい音楽をつくってみよう。ジャズ・ミュージシャンたちがそう考えたのがフュージョンの始まりで、画期的なムーブメントだったと言っていいと思います。
秋吉さんは、フュージョンはポップスだと言っていて、ジャズ・ミュージシャンがフュージョンをやることに懐疑的でした。一方、貞夫さんはフュージョンに新しい可能性を感じて、自分の音楽にそのスタイルを取り入れました。どちらが正しくどちらが間違っているということではありません。
しかし、あとから歴史を否定してしまうのはおかしいと思うんです。多くのジャズ・ミュージシャンが取り組んだスタイルであり、その音楽を聴いたたくさんの人がいる以上、ジャズの正史にしっかり位置づけられなければならない。それが僕の考えです。
──なるほど、次のお仕事はフュージョン本になりそうですね。楽しみにしています。
いやいや、書けるかどうかわからないし、書くなら退職してからでしょうね。それまでは新聞記者の仕事を真面目にまっとうしたいと思っています(笑)。
取材・文/二階堂尚
撮影/高瀬竜弥