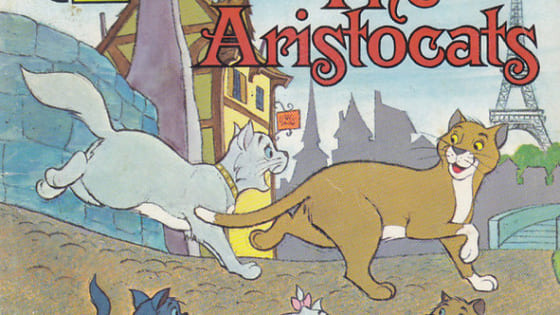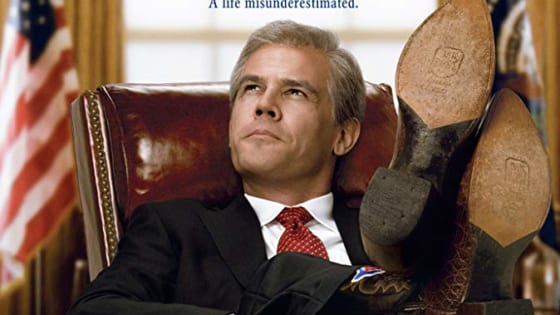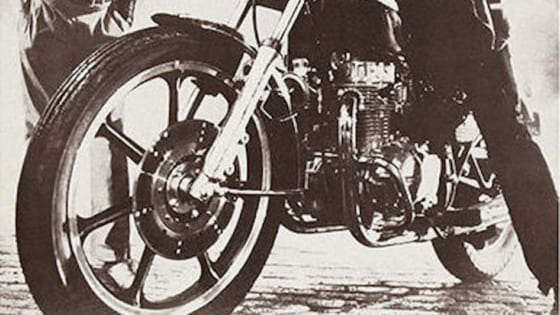投稿日 : 2016.08.05 更新日 : 2018.12.12
阿部和重【音楽/映画覚書】第8回『戦場のメリークリスマス』
文/阿部和重 写真/(c)大島渚プロダクション

今回は、坂本龍一に関連する作品を取りあげよとの注文が編集部より入った。該当する映画はいろいろあるが、本連載は微妙に筆者自身の回顧録みたいになっている面もあったりするので、懐かしの1本として1983年公開の大島渚監督作『戦場のメリークリスマス』を振りかえってみたいと思う。
公開当時は中学3年生だった筆者が『戦場のメリークリスマス』の情報に最初に触れたのは、『ビートたけしのオールナイトニッポン』聴取中だったように思うが(ロケ地となったラロトンガ島の名前を同番組ではじめて知ったというたけしファンは少なくないはずだ)、同時期に読んだスポーツ新聞の製作発表記事も印象に残っている。その記事でとりわけ強調されていたのは、配役の異色性だったと記憶している。
劇映画にミュージシャンやポップスターが役者として出るというのは、昔も今もなにも珍しいことではない。だれもが知っているビッグネームの出演作を挙げれば、ジョン・レノンなら『ジョン・レノンの僕の戦争』(1967)、ミック・ジャガーなら『パフォーマンス』(1970)や『太陽の果てに青春を』(1970)、ボブ・ディランなら『ビリー・ザ・キッド/21の生涯』(1973)などがあるわけだが、ついでに言えばこれらはどれも有名監督の作品でもあり、『戦メリ』もまたその系統に位置づけられるのはたしかだろう。
もっとも、主演のデヴィッド・ボウイや坂本龍一のみならず、ビートたけしやジョニー大倉や内田裕也や三上寛といったミュージシャン/ポップスターが大挙して出演している『戦メリ』の配役は、やはり異例といえば異例だったのだと考えられる。おなじくあまたの著名ミュージシャンがキャスティングされている先行作としては、ロジャー・ダルトリーが主役を務め、キース・ムーンやエルトン・ジョンやエリック・クラプトンやティナ・ターナーが出演している1975年のケン・ラッセル監督作『トミー』が有名だが、言うまでもなくあれはザ・フーの同名アルバムを映画化したロック・オペラ作品なのだから、そうした配役は当然の選択だったのだ。
他方『戦メリ』は、史劇といっても『ジーザス・クライスト・スーパースター』のようなミュージカルでもなければ、巧みな歌唱や楽器演奏がもとめられる役柄が用意されている内容でもない――デヴィッド・ボウイが賛美歌を口ずさむ場面があるとはいえ、特に歌唱力の発揮が要請される芝居ではなく、上手な歌い手として作中に登場するのはむしろ彼の弟役のほうだから、ミュージシャンが演ずる必要性の薄い役であることに変わりはない。そもそもがローレンス・ヴァン・デル・ポストの原作に基づいて製作された、太平洋戦争下の日本軍捕虜収容所での西洋人捕虜と日本軍人のあいだの葛藤劇を描いた『戦メリ』におけるミュージシャン/ポップスター偏重の配役は、周辺情報に触れるだけではその必然性がわかりにくかったのではなかろうか。
おまけにウィキペディアによれば、『戦メリ』の配役はもともと何人かの職業俳優に持ちかけていたところいずれも都合が合わず、何度かの変更を重ねた末にあの顔ぶれにおさまったとされている(デヴィッド・ボウイの役はまずロバート・レッドフォードにオファーされていたというのは、パンフレットかなにかにも書かれていたと筆者も記憶している)。つまりあの『戦メリ』出演陣は、たまたまの結果として生まれた組み合わせであるということだ(ちなみに映画においては配役が二転三転することも珍しい事態ではない)。
しかし仮にそうだとしても、『戦メリ』という映画がもたらす直接の印象に、紆余曲折の痕跡は見られない。むしろはじめから狙って組み立てた配役ではないかとさえ思える、独特のアンサンブルの妙がある。実際は紆余曲折の末に決まった配役を、あたかもすべて当初よりの狙い通りかと納得させてしまう密度の濃さが、できあがった映画からは感じとれるのである。『戦メリ』は決して傑作というわけではないが(監獄映画としてはスチュアート・ローゼンバーグの監督した傑作『暴力脱獄』を再構成した作品に見えないこともない)、あの配役から生み出されるなんとも微妙な芝居のありように触れるうち、絶対にこうでしかありえないと確信させられてしまうのは、なにもこちらの思い入れだけが原因ではないはずだ。
その確信は、どこから生まれたものなのだろうか。考えられるのは、ミュージシャン/ポップスター偏重の配役と戦争映画という題材とのミスマッチだ。ミュージシャン/ポップスターと日本軍人のイメージは、多くのにとって遠く隔たっているだろう(少なくとも公開当時の1983年には、両者を重ねる視点は一般的ではなかったにちがいない)。そしてそうしたイメージの隔たりがスクリーン上に示されるとき、多くの観客にとってまったく見慣れぬ人物像がうごめくことになり、結果的に奇妙な生々しさが作品にもたらされ、これしかないと納得させてしまう密度の濃さにつながったのではなかったか。
『戦メリ』で大島渚が試みた演出は、おそらくそうしたものであり、たまたまの結果や偶然を新たな創意につなげる才覚というものが、そこには認められる。そしてその、使える偶然を呼びこみつつ、見事な狙いに変えてしまう臨機応変な演出力というのは、映画づくりにおいては必須の技量なのであり、それはデジタル合成・修正の加工が当たり前となった今日でも変わらぬはずである。絶えず移ろう現実のなかで芝居を構成し、統御不能の自然の風景にカメラを向けることで試されているのは作家の受容性なのであり、機転なのだから。どこまで事前につくりこもうと、偶然は必ず入りこむものなのだ。

製品情報(Blu-ray)
タイトル:戦場のメリークリスマス (原題:Merry Christmas, Mr.Lawrence)
監督:大島渚
販売元: 紀伊國屋書店
Amazon
https://goo.gl/ptQfxC