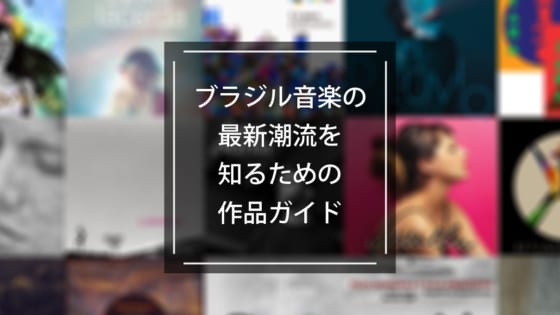投稿日 : 2021.10.22 更新日 : 2022.06.03
挾間美帆の新作と「ラージ・アンサンブルの歴史」を一気に解説 ─おすすめ作品リストも

挾間美帆の最新作─その中身は?
──アルバムの建て付け自体が非常にチャレンジングとのことですが、作曲や演奏の面で、彼女の “チャレンジ”を感じたところはありますか?
村井 リズムですね。たとえば4拍子とか3拍子だけじゃなくて、7拍子とか変拍子が入り混じったり、速い4ビートからディープなシャッフルになって、また違う拍子になったり。リズムの面はかなり冒険的だと思いますよ。
それから楽器の使い方も。ビッグバンドの基本的な動かし方というのは “サックスセクション対ブラスセクション” なんですね。つまりサックスが何か動くとブラス(金管)は別の動きをする、という演奏が普通なのですが、ときにはセクションをまたぐこともあります。
──セクションをまたぐ?
村井 そう、このアルバムにもそうした配置があって、たとえばサックスセクションの何人かと、トラペットセクションの何人かが、臨時にひとつのセクションを作って同じ動きをしたり、サックスセクションの中で3つに分かれるとか。そういった複雑な絡み方で、すごく面白い世界をつくり出している。
あとは、フルート、クラリネット、バスクラリネットといった木管楽器をサックスセクションの中で使って、すごく美しいものを作るとか。いろんなことをやっていますね。
──そうした書き方や手際に、先人への意識が見え隠れしている?
村井 そうですね。デューク・エリントンから、ギル・エヴァンス、スタン・ケントン、サド・ジョーンズ……それから、穐吉敏子とかマリア・シュナイダーまで。そうした偉人たちが、これまでビッグバンドという編成を使ってどうやって新しいサウンドを表現してきたのか。そうした財産みたいなものを、彼女は自分の曲の中でいろいろと試しているようにも思えます。
今回はトロンボーン5人でその中のひとりはチューバも吹き、トランペットとフリューゲルホーン合わせて5人、サックス5人にリズムが4人ですから、まあビッグバンドの標準編成と言っていい。彼女はそこで「どれだけ新しいことできるんだろう?」みたいなチャレンジをしていますよ。
ビッグバンドとラージ・アンサンブル
──「ビッグバンドの標準編成」というワードが出ましたが、昨今は “大人数で奏でるジャズ” をラージ・アンサンブルと呼んだりしますね。
村井 「ビッグバンド」「ジャズオーケストラ」「ラージ・アンサンブル」など、いろんな言い方がありますが、最近は「ラージ・アンサンブル」という言葉が定着したようですね。結局、何人いればラージなのか、そこは曖昧ですね。グラミー賞を見ていると6人編成でも入ったりしていますよね。
──ちなみにグラミーだと、現在の部門名は「ラージ・ジャズ・アンサンブル」ですが、60年代は「ラージ・グループ」という言い方をしています。その後、1972年から91年は「ビッグバンド」でした。ただ、なんとなくニュアンス的に、ラージ・アンサンブルとビッグバンドは違いますよね。
村井 そうですね。ラージ・アンサンブルというのは弦楽器が入っていても構わないし、なんだったらラージのうち、3人コーラスでもいいわけですよね。
ビッグバンドという言い方をしてしまうと、もう少し概念的には狭いという印象。特にジャズ・ビッグバンドというと、トランペット、トロンボーン、サックス+リズムセクションという、カウント・ベイシーなどの編成のイメージですよね。
あと、ビッグバンドというのは、ビッグバンドだけで演奏するというケースと、むしろオーケストラと同じだから、ソロの人が別にいるというケースもありますよね。歌手の後ろにいたり、フィーチャード・ソリストがいたり、あるいはダンサーという主役がいて、その後ろで演奏したり。
──ダンサーもOKですか。
村井 歴史的にはね、おそらく最初の主役はダンサーだったと思うんですよ。ジャズ・ビッグバンドの最初の形は軍楽隊で、当時のポップスを演奏していたんですね。1910年代にはジェームス・リース・ユーロップという黒人の軍楽隊の隊長がいて、彼の所属する軍楽隊が第一次世界大戦でヨーロッパに行って、たとえばパリなどで演奏していました。
つまり、このとき初めてヨーロッパ人にジャズを聴かせたんですね。その時代に、ヴァーノン・キャッスル夫妻という、映画にもなった男女のダンサーチームがいるんですよ。その2人のために、ジェームス・リース・ユーロップの軍楽隊は伴奏したそうです。
──おもしろいですねー。オペラやバレエの本拠地に、アメリカ産の新しい「音楽と舞踏」が伝わるという出来事。
村井 そうした軍楽隊が、だんだんジャズのビッグバンドに特化していって、1910年代の終わり頃にはすでにフランス人はジャズが好きになっていたといいますよね。
──ジャズが発祥したのはアメリカのニューオリンズと言われていますが、当時のニューオリンズはフランス領だったわけですよね。そのことを踏まえると、まるで “生き別れになった我が子が、立派な姿で目の前(フランス本土)に現れた” みたいな話。なんか歴史のロマンを感じますね…。
ビッグバンドの歴史
村井 一方、それとは別に1910年代の終わり頃には、ポール・ホワイトマン・オーケストラというのがありました。ポール・ホワイトマンはもともとクラシックの人なのですが、彼のやっていたことは、いわば今のメトロポール・オーケストラ・ビッグバンド(注:挾間美帆が常任客演指揮者を担当するオランダのバンド)と同じですよね。弦楽器セクションが大勢いて、それと一緒に管楽器主体のビッグバンドがあって、それを一緒にやりましょうということです。

村井 ポール・ホワイトマン・オーケストラが演奏するのは当時流行していたポップスやジャズの曲なのですが、注目すべきは、ジョージ・ガーシュウィンによるアメリカのオリジナルのクラシック曲「ラプソディ・イン・ブルー」。これは、コンサートのためにホワイトマンがガーシュウィンに委嘱した曲だ、ということです。
──そうだったんですね。有名な曲ですが、そんな経緯があったとは。
村井 ジョージ・ガーシュウィンはピアノが上手い作曲家なのですが、オーケストレーションができなかった。そこで「ラプソディ・イン・ブルー」をオーケストラにするときに、ホワイトマン楽団の専属作家だったファーディ・グローフェというクラシックの作曲家に協力してもらったんですね。つまり、これはグローフェと一緒に作った曲なんです。
ポール・ホワイトマン・オーケストラというのは数分間のポップスもやりつつ、クラシックとジャズをうまく組み合わせたような「ラプソディ・イン・ブルー」のような10分、20分かかるような曲も20年代にやっているんですね。
──大衆受けもキープしながら、かなり先鋭的なこともやってたんですね…。
村井 ただし、20年代には人気があったのですが、だんだんアフリカン・アメリカンのジャズが本物だと言われるようになると、彼らはインチキとか偽物といわれるようになる。しかし、今にして思うと、彼らはオリジナルなことをやっていたわけです。そういう意味では、現代のラージ・アンサンブルは、ポール・ホワイトマンが蘇った感じがしますよね。
ご本人がどう思っているのかはわかりませんが、挾間美帆はポール・ホワイトマンがやっていたことの21世紀バージョンみたいに捉えることもできると思うんです。
次ページ>>デューク・エリントンの異常さ