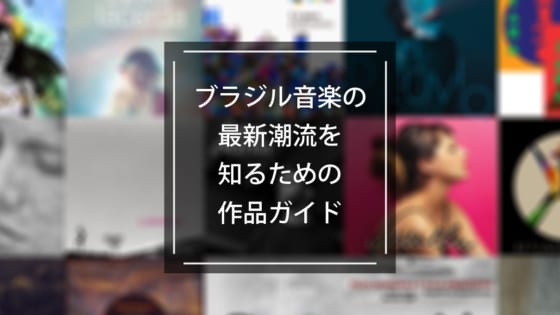投稿日 : 2021.10.22 更新日 : 2022.06.03
挾間美帆の新作と「ラージ・アンサンブルの歴史」を一気に解説 ─おすすめ作品リストも

デューク・エリントンの異常さ
──ポール・ホワイトマンが「ラプソディ・イン・ブルー」をやり始めた頃には、デューク・エリントン・オーケストラも登場しますよね。
村井 エリントン楽団のスタートは1920年代半ばですね。こちらは基本的に弦楽器は入ってない編成。他人の曲も演奏しつつレパートリーの中心は自分の曲で、これまで誰もやったことがなかった楽器の使い方やハーモニーをつくり上げていきます。聴くと「なんか変だよね」と感じることを、30年代からやっていた。その特有の響きが、ジャズを新しいところに持っていったんですね。
たとえば「キャラバン」という有名な曲がありますが、いくつもあるエリントンの録音の中には、不協和音の塊が平行移動しているようなバージョンもあったりします(笑)。

村井 同じ時期に人気を博したベニー・グッドマンと比べると、圧倒的に不協和音。だけどなんかかっこいい。当時のデューク・エリントンはダンスの伴奏なども普通にやっていたそうなのですが、いま聴くとやはり飛び抜けて変です。彼と比べるとカウント・ベイシー・オーケストラは、スウィングするけどハーモニーとしては普通なんですよね。
──エリントンって、かなり特殊だったんですね。てっきりビッグバンドの保守本流だと思い込んでいました。
村井 現代のアマチュアのビッグバンドで、カウント・ベイシーの楽曲を演奏しているバンドは世界中に何百も何千もいて、その多くがきちんと演奏できています。ところが、デューク・エリントンの楽曲を、当時の彼らと同じように演奏できているバンドはほとんどいません。
──え? どういうことですか?
村井 いくつか理由があって、まず、ちゃんとした楽譜がない。デューク・エリントンの楽譜の書き方は複雑すぎて、なかなかトランスクライブ(耳コピ)できないんです。たとえばサックスが5人一斉にパーッと吹くとき、エリントンは時としてバリトンサックスに高い音を出させる。そうすると、かなり変な感じになります。音色が普通ではないんですね。無理していますから。そういったことを曲中いろんなところでやるので、耳で聴いているだけだと「なんか変なんだけど、これどう鳴っているんだ?」と、わからなくなるようです。
──すごいオリジナリティの出し方ですね(笑)。
村井 生前のデューク・エリントンが使っていた楽譜はスミソニアン博物館に保管してあるそうですが、そう簡単に見せてくれないそうです。もちろん、それを借りてコピーもできない。現在、いくつか信頼できる楽譜も売られていますが、それは現代のミュージシャンが必死で耳コピして書いたものなんです。

村井 さらに、デューク・エリントンは同じ曲を何度も書き換えます。同じ曲の演奏でも、1年後には全然違っている、みたいなことも起きるわけです。ニューヨークにあるリンカーン・センターという総合芸術施設では、エリントンの曲をビッグバンドの優秀な人が耳コピしているのですが、それぞれの楽譜には曲名と「19◯◯年◯月◯日バージョン」と書かれています。
──エリントンの音楽を本気で再現するとなると、それなりの覚悟が必要なんですね…。
村井 エリントンは個性的な音色を持つメンバー、たとえばジョニー・ホッジス(アルト・サックス)やクーティー・ウィリアムズ(トランペット)のことを意識して譜面を書いているということもあり、なかなか本人たちのような音にはならない。もちろん、普通に演奏が難しいということもあるんですけどね。
──エリントンと同じ時期に、カウント・ベイシー楽団も人気を博しました。しかも、こちらは現在のラージ・アンサンブルにつながる重要な人間関係がありますね。
村井 そうですね。カウント・ベイシーが30年代後半ぐらいにバッと出てきたとき「ものすごく気持ちよくスウィングする」ということで、瞬く間に人気者になった。50年代にこのバンドに在籍していたサド・ジョーンズがのちに独立してつくったのが、前出のサド・ジョーンズ=メル・ルイス・ジャズ・オーケストラです。

──トランペット奏者だったサド・ジョーンズと、ドラム奏者だったメル・ルイスが結成したグループですね。
村井 彼らはカウント・ベイシーゆずりのスウィング感と、エリントン的な曲の面白さも兼ね備え、さらに60年代以降のモード・ジャズ的な作法も加味して、ハーモニー的にはかなり難しいことをやります。しかも、サド・ジョーンズはカウント・ベイシー・バンドの出身ですから当然、気持ちよくスウィングもする。リズムセクションにも素晴らしい人材を揃え、管楽器の演奏者も当時のモダンジャズの重要どころが在籍していました。
で、このグループに在籍していたのが、前出のボブ・ブルックマイヤー。彼はもともとスウィング・ジャズ出身の人なのですが、作る曲はハーモニー的には高度で難しく、洗練されていてモダン。そういう流れが60年代以降ビッグバンドの主流になっていきました。
──サド・ジョーンズ=メル・ルイス楽団は、78年に(サド・ジョーンズが欧州に移住したため)メル・ルイス・ジャズオーケストラとなり、このバンドはメル・ルイスの死後(1990年)もヴァンガード・ジャズ・オーケストラとして続行して、現在に至りますね。
村井 そこでピアノを弾き、曲も提供したのがジム・マクニーリー。
──さっき話に出た “挾間美帆がスペシャルサンクスに入れた3人”が、ここで一気に出揃いました。
ビバップ時代のビッグバンド軍師たち
──デューク・エリントン、カウント・ベイシー以降はどんなバンドが?
村井 たとえば40年代に人気があったスタン・ケントン楽団。彼らはロサンゼルスを拠点に、なんでも演奏するバンドだったのですが、スタン・ケントン自身はかなり変わってるというかチャレンジングな人です。
彼は50年代のはじめぐらいにイノベーション・イン・モダン・ミュージック・オーケストラという、ストリングスを含む40人以上の楽団を結成して、無調の曲を演奏していたようですね。ほとんどイーゴリ・ストラヴィンスキーじゃないか! みたいな曲をね(笑)。それでもって、50人編成ぐらいで全米ツアーをやって大損したそうです。

──チャレンジングにも程があるぞ、と。しかしスタン・ケントンもエリントン同様、そこまでユニークな印象を持っていなかったので意外です。
村井 そうやって彼がアバンギャルドなことをやっていた時期に、スタン・ケントン楽団に曲を提供していたのがピート・ルゴロという人物で、この人はマイルス・デイヴィスの『クールの誕生』のプロデューサーでもあります。
──へぇ〜!
村井 つまり、マイルスがニューヨークでやっていたのは、ピート・ルゴロがケントン楽団でやっているようなことをわかりやすくして、9人くらいの小編成にして演奏した感じなのだと思います。

村井 さらに、40年代はじめ頃のニューヨークにはクロード・ソーンヒル・オーケストラという、白人ダンスバンドがありました。美しい演奏で知られていたのですが、そこにアレンジャーとしてギル・エヴァンスが入るんですね。彼は新しいことをいろいろやりたがった。クロード・ソーンヒル・オーケストラは、もともとフレンチホルンが2人いたため、クラリネットも合わせてクラシックっぽいアレンジもできる。で、これを使ってもう少し面白いことできないか? ということで、ギル・エヴァンスはたくさん譜面を書いたようですね。
それらの曲は今聴いてもかなり尖ったハーモニーが出てきておもしろいし、「ドナ・リー」なんかも演奏しているんですよ。
──“チャーリー・パーカーの曲” として有名な、ビバップのアンセムですね。
村井 クロード・ソーンヒル・オーケストラはあの曲を、チャーリー・パーカーが出てきてすぐにギル・エヴァンスのアレンジで演奏しているんです。「ドナ・リー」を書いたのは実はマイルスで、ギルとマイルスの付き合いはそこから始まったらしいですね。その影響は以降のビッグバンドへと続いていきます。
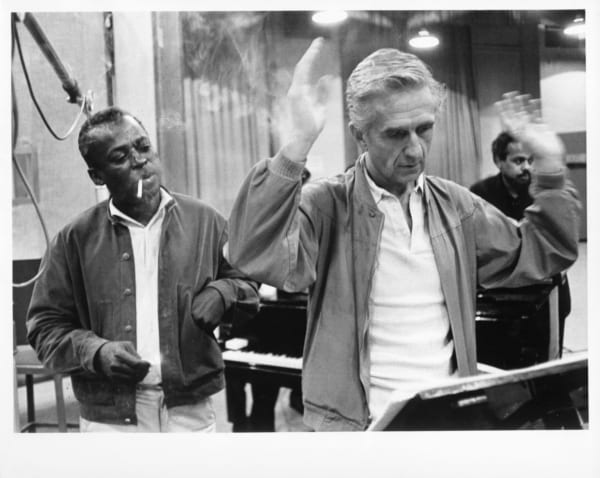
村井 で、そんなギル・エヴァンスのアシスタントをやっていたのが、マリア・シュナイダーですからね。
──現代のラージ・アンサンブル界における最重要人物のひとりですね。
村井 彼女はギル・エヴァンスのアシスタントをやりながら、同時にボブ・ブルックマイヤーにも習っていて、両者の影響を強く受けている人物。もう60代になりましたが、いまだに若い世代にものすごい影響を与え続けていますよね。
──挾間美帆もその影響を受けたひとり。というわけで、ここまで “挾間美帆の新作を読み解くうえで重要な人物とバンド”を挙げつつ、ビッグバンド史の要点を掻い摘んでお話ししていただきましたが、それでもこのボリュームになってしまうんですね。
村井 本当はもっといろいろありますけどね。とりあえずここまでの話をまとめると、1910年代の軍楽隊に始まって、20年代にポール・ホワイトマンがクラシックとジャズを融合させようとし、30年代にエリントンが不思議なハーモニーを奏で、カウント・ベイシーが生き生きとスウィングし、その後、サド・ジョーンズは両者の良いところを組み合わせ、さらに60年代のモードが入ってきて発展していく。もちろん、その間にも横からスタン・ケントンほかいろんな作家たちが刺激を与えながら今に至る。といった感じでしょうか。
ここでは「20年代のフレッチャー・ヘンダーソン楽団から始まり、30年代のベニー・グッドマンへと続く流れ」のことは割愛していますが、実はそっちが「スウィングするビッグバンド」という点では主流だったりします。
次ページ>>グラミーから見えるビッグバンド事情