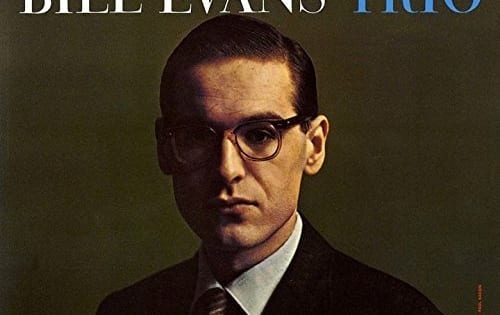投稿日 : 2018.12.06
【山本耀司】19年ぶりの音楽ライブで「今の世の中や若者たちに、伝えたいことがある」
取材・文/宇野維正 撮影/山下直輝

MENU
Yohji Yamamotoのデザイナーである山本耀司が、19年ぶりに音楽ライブをおこなう。ファッションシーンを牽引し続ける山本が、ミュージシャンとして何を表現するのか、なぜいまライブステージに立つのか? ブルーノート東京での公演を間近に控えた同氏に話を訊いた。
パリコレの音楽も自身で制作
──今回、19年ぶりのライブを開催されるわけですが、まず誰もが思うのは「一体どのような内容になるんだろう?」ということで。近年はパリコレクションで流す音楽をご自身で作られてますよね?
「それまでは既成の曲でコレクション音楽を構成していたんですけど、5~6年くらい前から観客がその曲のセンチメント(Sentiment:感情)に影響されてしまうのはちょっと嫌だなと思うようになって。じゃあ、もう自分で作っちゃおうかなって。
最初は、見ている人が服に集中しやすいように、カメラのシャッター音を消してくれる程度の雑音だったんですけど、その雑音に音符がついて、詞がついて、曲になっていった感じです。そうやって出来上がった曲のストックが増えてきたので、ライブで披露しようかという話になったんです。
けど、まさかBlue Note Tokyoが『どうぞ』と言ってくれるとは思わなかった。自分も友達のミュージシャンのライブに招かれてよく訪れる大好きな場所だったので、まさかと(笑)」
──ということは、耀司さんが’90年代にやられていた音楽の延長上にあるものではない?
「そうですね」

──ただ、耀司さんがコレクションのために作ってきた音楽も、完全なインストゥルメンタル・ミュージックではなく、そこには言葉があり、歌がありますよね。
「ライブの準備をしている中で、やはり歌の比率は上がってきました。だから9割くらい、ほとんど歌うことになると思います。ライブをやるからには、そこにはメッセージのようなものが必要になると思いますので」
祈りの歌と生活の歌が起点
──メッセージとは、一体どういうものなのでしょう?
「音楽から大きな衝撃を受けた経験が、自分には2度あるんです。ひとつは、40年くらい前のことですが、ヨーロッパに行き始めるようになった頃。モロッコのマラケシュで、夕方、丘の上でひとりのお爺さんがコーランを唱えていたんです。それがなんとも言えない美しいメロディで。コーランって、誰かに聴いてもらおうと思っているわけではなくて、神と対話をするための言わば祈りの歌ですよね。
もうひとつは、これも20年以上前のことですが、シルクを漆黒に染めたくて、奄美大島に泥染めの風習が残っているという噂を聞いて出向いたときのこと。奄美では、若い男の子たちが4~5人で泥染めの研究を続けていたのですが、既製服での実用化が難しくて。そこで西表島に行くことをすすめられて、ある農家の方の家でお世話になったんです。
夜には泡盛や山海の珍味をご馳走していただいたんですけど、その時に農家のご主人が三線を持ち出してきて、歌を歌ってくれました。途中から奥さんとの掛け合いも始まって、全部で30分くらいだったと思いますが、ずっと泣いていましたね。そこには深く胸に染み入る生活の歌がありました」
──祈りの歌と生活の歌。
「どちらも売るために作られた音楽ではなくて、その人たちの生活そのものですよね。だから音楽をやるなら、自分自身の生活の歌でなくてはいけないという気持ちが、’90年代に音楽をやり始めた頃からありました。ジャンルで言うと、自分が最も尊敬しているのはブルースです」

──ジャズはダメですか(笑)?
「ブルースの感覚がまだ残っている、ある時代までのジャズは好きです。自分が好きな音楽は、ブルーで、暗くて、泥臭い音楽なんです」
生きることは大変だし辛い
──ただ、今回は新しく作った曲もたくさん披露されるわけですよね?
「そうですね」
──となると、そのブルースにのるのは、現在の耀司さんの中から出てきた言葉。いま、ご自身が考えられていることや、見ている世界を反映されたものになるわけですよね?
「当然そうなります。詞はすべて、日本語でも英語でもフランス語でも、自分で書きます。メッセージと言えるほど立派なものになっているかはわかりませんが、今の世の中や、今の若者たちに対しての物言いになってますね。伝えたいことがあるんだ、っていう」
──ライブに来ることができる人は限られているので、そのエッセンスのようなものをここで少し教えていただけますか?
「簡単に言うと、生きることは大変だということ。生きるって、辛いじゃないですか。それを音楽を通じて分かり合いませんか? っていうことですね。
現代は完全にコンピュータとインターネットの時代。Wi-Fiのように目に見えないものではなくて、地面に足をつけて歩こうよ、と。自分は何十年もコレクションを発表していますが、パターン(服の型紙)はすべて手で引いています。今はどのアパレル会社もCADと呼ばれるコンピュータを使ってパターンを作っているので、地に足をつけるということは、自分がこれまでずっと続けてきた生き方でもあります」
──今は車のデザインも全部そうですよね。
「コンピュータで作ると全部似てきますが、自分の手で線を引いたデザインはまったく違うんです。うちの服はいまだに全部、手を動かしてデザインをしています。そうすると、そこには線を引いた人の人間性のようなものが本人の意思とは関係なく滲み出てくる。今回それを音楽でもやってみようということです。曲を作る方が服より大変ですが(笑)」
──最も違うのはどういう点ですか?
「ファッションは映画のようにチームで作るものですが、音楽は違う。もちろん、バンドのメンバーは手伝ってくれますが、全責任は歌う自分にある。今、リハーサルでも大変な思いをしてます。歌唱力がなくて(笑)」

黒人文化には昔から仲間意識がある
──2010年代に入ってから、ルー・リードやデヴィッド・ボウイといった、耀司さんから影響を受けてきたミュージシャンたちが相次いで亡くなりました。そのことは、今回のライブ活動の再開を後押しする要因のひとつにもなったのでしょうか?
「ヴィム・ヴェンダースを通じて交流を深めるようになったルー・リードとはいくつもの大切な思い出がありますが、ミュージシャンに限らず、今、自分と近い年齢のアーティスト、あるいはもっと下の世代のアーティストがどんどん亡くなっている。『だからこそ』という気持ちは確かにあります。こうして生かされているからには、自分も何かやらなくてはと。ちょっとかっこつけすぎかもしれませんが、たったひとりでもいいから誰かを勇気づけたい。それが本当の気持ちです」
──一方で、いまやカニエ・ウェストやファレル・ウィリアムスやリアーナなどを筆頭に、ミュージシャンがファッション・ビジネスに参入するようになって久しいですよね。Y-3(ヨウジヤマモト社とアディダス社の協業ブランド)はその先駆的な試みだったわけですが、今ではスポーツブランドにラッパーが自分のラインを持っているというのも珍しいことではなくなりました。そのような時代の変化は、耀司さんの目からはどのように映っていますか?
「2~30年前まで、アートの世界では最上位が絵画、次に音楽、そしてずっと下に映画が位置されていて、ファッションなんてものはランク外でしたから。今のようにスマートフォンをみんなが持つようになってから全部がフラットになった。これは非常に大きな変化だと思います。音楽を好きな人がファッションをやる、ファッションを好きな人が音楽をやる、良いことだと思います。それに19世紀後半のブルース時代から黒人文化というのは大体正しいんです。正しいというか、自分は昔から仲間意識がある。みんな『Hey, Yohji!』って感じで近寄ってきてくれるし(笑)」
林立夫は親友の弟なんです
──ドラムの林立夫さん、ベースの伊賀航さんを筆頭に、今回のライブのバンドにはものすごいメンバーが集まってますよね。

「そうですね。自分ではわからないんだけど(笑)。林立夫は、小学校からの大親友の弟で。彼の兄貴とはいつも一緒にいたので、立っちゃんが幼稚園に行くか行かないかの頃から知っていて」
──そうだったんですね(笑)。
「ギターの網元次郎は、年4回のコレクション音楽を作るときにいつも手伝ってくれる相棒。古賀芽衣は、今年のメンズとレディースのコレクション音楽に参加してくれました。バンドのメンバーは、みんな自分に優しいんです。おかげでこんな僕でもステージに立つことができる(笑)」
──今回はライブだけで、音源をレコーディングする予定はないんですか?
「予定はありません。ライブとレコーディングとではやる仕事の量が全く違いますからね。時間がいくらあっても足りないのです(笑)」
Yohji Ymamoto × Live
http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/yohji-yamamoto/
日時:2018年12月10日(月)
場所:ブルーノート東京(東京都港区)