TAG
エリック・クラプトンオーティス・ラッシュブルースモントルー・ジャズ・フェスティバルライブ盤で聴くモントルーレッド・ツェッペリンローリング・ストーンズ
投稿日 : 2020.07.20
文/二階堂 尚

MENU
「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。
B・B・キングが切り拓いたモダン・ブルースの世界を支えた一人であり、ミュージシャンに対する影響力という点ではB・Bをも凌いだ巨人、オーティス・ラッシュ。1986年のモントルー・フェスの彼のステージに飛び入りしたのは、彼を師と仰ぐあのギタリストだった。
あれは1990年だったか。千葉の市川駅前のライブハウスでオーティス・ラッシュを見たとき、あのモダン・ブルース界のスターが、こんな小さなハコで、こんな少人数の観客の前で演奏するのかと驚いたことをよく覚えている。観客は10人もいなかったと思う。むろん彼は手を抜くことも、ふてくされることもなく、サックスを含む少人数のバンドで素晴らしい演奏を聴かせ、最前列で一人で見ていた美しい女性にさりげなくギター・ピックを渡してステージを去っていった。そのライブハウスも、今はもうない。

60年代の英国ブルースの名作『ジョン・メイオール&ブルース・ブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン』の冒頭を飾っていたのは、オーティス・ラッシュの「オール・ユア・ラヴ」のカバーだった。ビートルズの時代を力技で終わらせたレッド・ツェッペリンのファースト・アルバムには、やはりラッシュの「アイ・キャント・クイット・ユー・ベイビー」が収録されている。エリック・クラプトンの武道館公演を収めたライブ・アルバム『ジャスト・ワン・ナイト』におけるラッシュの代表作「ダブル・トラブル」は、これまでのクラプトンのブルース・カバーのベストの一つと言っていい名演である。これはのちの話だが、クラプトンはキャリア初のオール・ブルース・カバー・アルバム『フロム・ザ・クレイドル』をラッシュの「グローニング・ザ・ブルース」で締めくくっている。最近では、ローリング・ストーンズが『ブルー&ロンサム』で「アイ・キャント・クイット・ユー・ベイビー」を取り上げていた。
60年代のロック・ミュージシャン、とりわけ英国のミュージシャンにとって、オーティス・ラッシュは別格と言っていい存在で、その影響力はロバート・ジョンソンやマディ・ウォーターズすら凌ぐものだった。クラプトンやジミー・ペイジやキース・リチャーズが師とあがめるようなミュージシャンが、極東の小さなライブハウスで、10人に満たない観客の前でプレイする。それがブルースというジャンルが置かれているポジションであった。それは今もそう変わってはいないだろう。
しかし、1986年のモントルーのオーディエンスは、オーティス・ラッシュというブルース・マンがどれほどの人かということをよく知っていた。そして、ブルースという音楽の素晴らしさを。
満場の拍手とフェスのプロデューサー、クロード・ノブスの煽りに背中を押され、ラッシュは冒頭から一気にギアをトップに入れる。曲名もそのまま「トップス」である。最初の2曲のインストルメンタルに続いて、B・B・キングの曲だがむしろラッシュのレパートリーとして知られる「ギャンブラーズ・ブルース」、エレキ・ギターの始祖、T・ボーン・ウォーカーの「ミーン・オールド・ワールド」といった有名曲に、自身の比較的新しい曲を交えて会場を大いに沸かせる。
ギターのネックを絞るようにしてチョーキングする、いわゆるスクイーズ・ギターの名手として知られるオーティス・ラッシュだが、そのスタイルのオリジネーターであったB・B・キングとの最大の違いは、ラッシュが左利きだったことである。彼は、アルバート・キング同様、右利き用のギターの弦を張り替えずに左手で弾く。当然、弦の順番は逆となり、高音部のチョーキングは、弦を「押し上げる」のではく「引っ張り下げる」ことになる。人間の指の構造上、より力が入るのは後者だから、チョーキングはおのずとダイナミックでレンジの広いものとなる。

英国のブルース研究家であるポール・オリヴァーは、『ブルースの歴史』という本(米口胡訳/晶文社)の中で、ラッシュやアルバート・キング、バディ・ガイら、B・Bに続くギタリストたちについて、こんなことを書いている。
「(ラッシュらは)B・B・キングがひろめたテクニックに磨きをかけて、長いすすり泣きのような音を、あざやかな音の滝となって流れ落ちるす速い(ママ)ランと対置してみせる。音を爆発させ、つむじ風にし、閃光のようにひらめかせながら、脈打つような音を増幅したヴィブラートで短いフレイズをくり返し、ボリュームは最大にしておくのである」
詩的すぎて何を言っているのか判然としないが、フィーリングだけははっきり伝わる文章である。ラッシュのギター・プレイをひとたび聞けば、この説明のニュアンスが非常によくわかる。
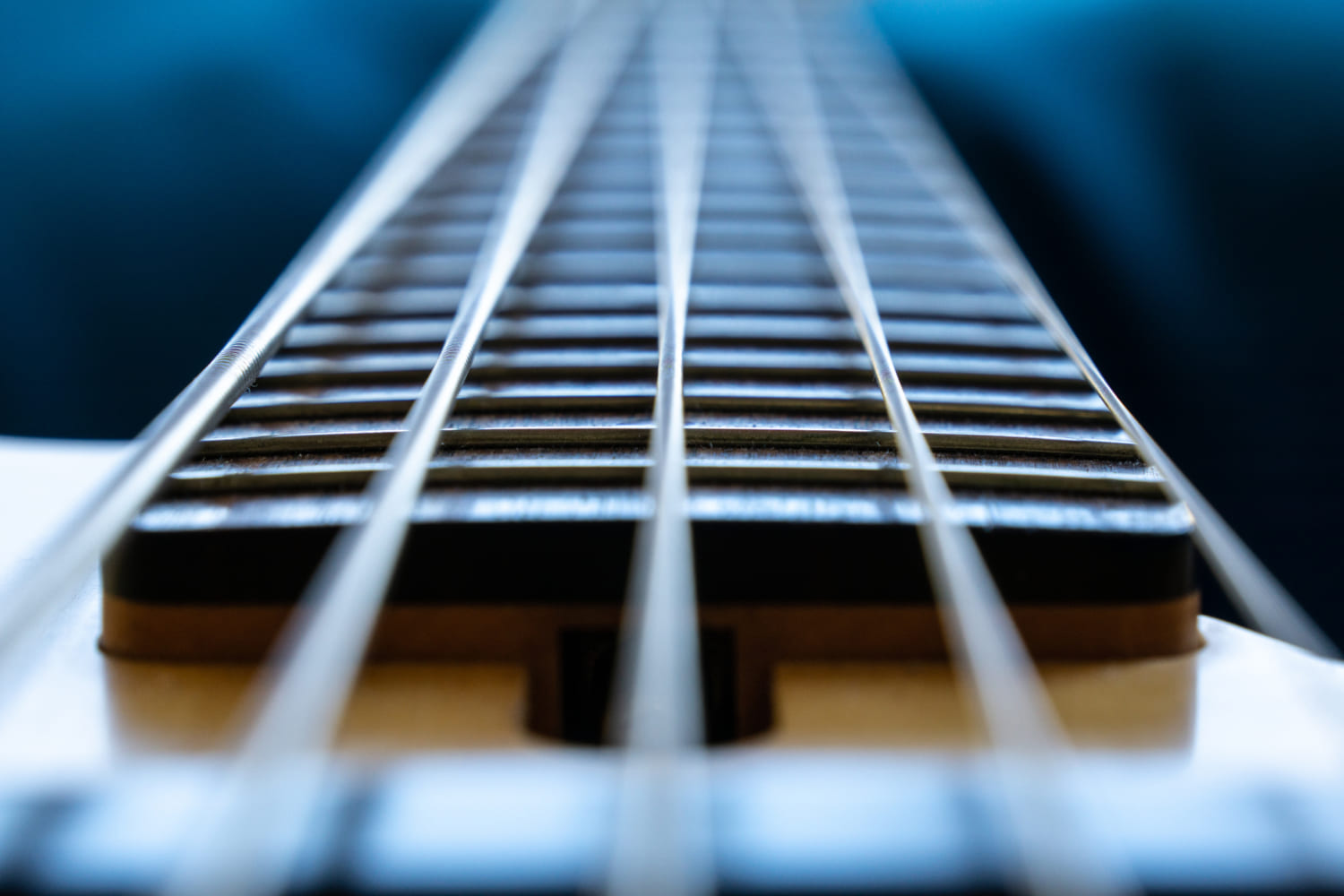
ラッシュのもう一つの魅力は官能的なふくよかさをもった声で、ロック・ミュージシャンの中でラッシュに最も強い影響を受けたと言っていいクラプトンは、ギター・スタイルだけでなく、ボーカル・スタイルも明らかにラッシュを手本としている。その影響はほとんど身体化していて、彼の声はときにラッシュの声と区別がつかなくなる瞬間があるほどだ。その「高弟」が「師」のステージにサプライズ・ゲストとして登場するのは9曲目からである。彼もこの年のモントルー・フェスに招聘されていたアーティストの一人だった。映像を見るとクラプトンの顔がやや紅潮していることがわかるが、これは緊張のためではなく、緊張を和らげるためにステージ裏で一杯ひっかけてきたためだろう。この時期の彼が重篤なアルコール中毒であったことは、以前にこの連載で言及したとおりである。
アルバート・キングの有名曲で、クラプトンも83年の『マネー・アンド・シガレッツ』で取り上げていた「クロスカット・ソー」から子弟セッションは始まる。CDではカットされているが、映像を見るとこの曲が終わった後、ラッシュがクラプトンに「ダブル・トラブル演るか?」と話しかけていることがわかる。むろん、クラプトンにとってこの曲が特別であることを知っていての振りである。ラッシュはワン・コーラス目のボーカルをクラプトンに譲る。続く曲もやはりクラプトンにゆかりのある「オール・ユア・ラヴ」で、どうやらラッシュはクラプトンに花を持たせるレパートリーをあえて選んでいることが明らかになる。
ラッシュは我を全面に押し出すタイプのミュージシャンではなかった。それゆえに、シカゴ・ブルース・シーンにおける盟友であったバディ・ガイに大きく水をあけられることになったのだとポール・オリヴァーは言う。
「音楽的にはなんの価値もないおどけぶりや娯楽性を考えたショウマンシップがガイを大変な人気者に仕立てたのに対して、ラッシュのずっと控え目な性格は見世物に対する需要には向いていなかった」(同上)
実力や知名度に比して録音作品が少なかったのもその控え目な性格のためだったが、彼の声やギターには、人格の奥底からほとばしる伏流水のようなまろやかな滋味があった。その滋味は、モントルーのステージでも十分に味わうことができる。最後にやはりシカゴのブルース仲間であったルーサー・アリソンが登場し、ステージを大いに盛り上げて70分ほどの演奏を大団円のうちに終結させる。
2000年代に入ってからは、脳梗塞の後遺症でほとんど演奏することができなくなったラッシュだが、彼に対するミュージシャンやファンからのリスペクトが絶えることはなかった。2016年、ラッシュが活躍したシカゴ市は、6月12日を「オーティス・ラッシュの日」にすることを発表した。その2年後、彼は静かに息を引き取ったのだった。

『ライヴ・アット・モントルー1986』
オーティス・ラッシュ&フレンズ
■1.Tops 2.I Wonder Why 3.Lonely Man 4.Gambler’s Blues 5.Natural Ball 6.Right Place, Wrong Time 7.Mean Old World 8.You Don’t Love Me 9.Crosscut Saw 10.Double Trouble 11.All Your Love (I Miss Loving) 12.Every Day I Have the Blues
■Otis Rush(vo,g)、Eric Clapton(vo,g)、Luther Allison(vo,g)ほか
■第20回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1986年7月9日

【アルバート・キング】ギターの音を「肉声」にした偉大なブルースマン ─ライブ盤で聴くモントルー Vol.64
投稿日 : 2025.11.17

【ソニー・ロリンズ】半世紀にわたってジャズ界を牽引した最後のモダン・ジャズ・ジャイアンツ─ライブ盤で聴くモントルー Vol.65
投稿日 : 2026.01.19

【ジョニー・キャッシュ】唯一無二の低音ボイスで聴衆を虜にしたカントリー界の巨人─ライブ盤で聴くモントルー Vol.63
投稿日 : 2025.09.16

【ユッスー・ンドゥール】世界を舞台に躍動するアフリカ音楽界のスター─ライブ盤で聴くモントルー Vol.62
投稿日 : 2025.07.22