TAG
ギル・エヴァンスジョージ・ガーシュウィンデューク・エリントンビリー・ホリデイポーギーとベスマイルス・デイヴィスミンストレル・ショー連載「ヒップの誕生」
投稿日 : 2023.04.04 更新日 : 2023.06.19
文/二階堂尚

MENU
日米の20世紀裏面史とジャズの関係をディグする連載コラム!
ジョージ・ガーシュウィンは、生涯の大作『ポーギーとベス』をオペラ化するにあたって、原作の舞台となったサウス・カロライナ州を訪れ、黒人コミュニティに身を投じた。原作である小説に描かれた黒人の生活を肌身で感じることで、「幻想の黒人」のイメージを払拭するためである。そうして「ユダヤ人作の黒人オペラ」は完成した。作中の数々の名曲は、のちに多くのジャズ・ミュージシャンに取り上げられ、現在まで歌い継がれるスタンダード・ソングとなったのだった。
アメリカ東海岸の港湾都市チャールストンに生まれたデュボース・ヘイワードが、自身の故郷を舞台にした小説『ポーギー』を上梓したのは1925年である。ジョージ・ガーシュウィンは翌年にその小説を読み、ヘイワード夫妻と会う機会もあったようだ。ヘイワードの妻ドロシーは劇作家で、夫妻は27年に『ポーギー』を舞台化している。

ガーシュウィンは早い段階からこの物語のオペラ化を構想していたが、実際に着手するまでに8年の時間を要した。理由はたんに多忙だったからだろう。しかし、その仕事は始まりから壁にぶつかることになった。先んじてこの作品をミュージカルにする企画を立てている人物がいることが判明したからだ。ガーシュウィン作の「スワニー」をヒットさせたユダヤ人シンガー、アル・ジョルソンである。
アルはミンストレル・ショー仕込みのブラック・フェイスで自ら主人公の黒人ポーギーを演じるつもりでいた。音楽担当として名前が挙がっていたのは、ガーシュウィンが敬愛したジェローム・カーンである。もし、『ポーギー』がアルの主演でミュージカル化されていたら、この作品がポピュラー音楽の歴史に名を残すことはなかっただろう。白人が黒塗りで黒人を演じる意匠は、公民権運動以降、許容される表現ではなくなったからである。現在ではアル・ジョルソンの名も、ミンストレル・ショーという芸能への評価も完全に地に落ちている。

幸いと言うべきか、そのアル・ジョルソンのプランは頓挫し、ガーシュウィンは『ポーギーとベス』の実現に向けて行動を開始した。1933年、彼はあらためて『ポーギー』を観劇し、その後物語の舞台であるサウス・カロライナ州チャールストンに向かったのだった。
『ポーギー』は、先天的に両足が不自由で、物乞いで日々を凌いでいるポーギーと、殺人を犯したヤクザ者の情婦であったベスという女の物語である。登場人物は警察などを除いてすべて黒人で、彼・彼女らはかつて富豪の住まいだった中庭つき三階建てレンガ造りの建物に住み着いている。長屋となったその建物は「なまず横丁(Catfish Row)」と呼ばれている。原作者は、物語の舞台である貧しい港町を「時というものによって破壊されないうちに、むしろ忘れ去られてしまったというような、古い美しい町」(齋藤數衛訳)と表現した。
作家が自ら生まれ育った故郷を描く筆致は臨場感に溢れ、とりわけハリケーンが港町を襲う場面の迫力には息を飲む。現在手軽に読める日本語訳がないのは、おそらく原文に難解な黒人英語が頻出するからで、1956年に東京ライフ社から出版された『ポギーとベス』の訳者である齋藤數衛も、「意味不明の箇所が若干あった」とあとがきに記している。
ガーシュウィンが絶対に避けようとしたのは、この作品をミンストレル・ショーやスティーブン・フォスターの歌の世界のような「白人の手になる幻想の黒人の物語」にすることだった。彼は二度にわたってチャールストンに赴き、黒人教会で讃美歌を聴き、苺や蟹や蜂蜜を売る行商人の声に耳を傾け、離島にコテージを借りて「ガラ」の世界に身を浸し、シャウティングと呼ばれる黒人の集団パフォーマンスに参加した。ガラとは、サウス・カロライナ州島嶼(とうしょ)部の、アフリカの言語や文化が残った黒人コミュニティを意味する。
すべては、黒人の文化や音楽に対する一方的な思い込みを払拭し、小説に描かれた世界をじかに肌身で感じるためだった。やはりユダヤ人であったレヴィ=ストロースのような文化人類学者の手つきで、ガーシュウィンは『ポーギー』の物語を自分のものにしようとしたのだった。
ガーシュインは、南部の自然と黒人コミュニティのなかに残る、アフリカ伝来のプリミティヴな集団パフォーマンスや生活習慣のなかに命を投げ出すようにして飛び込み、みずからを全面的に解放したうえで、おのずから内側から湧き起こってくるもの、すなわち「ジャズ」に『ポーギーとベス』の音楽的根拠を求めようとしたのである。(『ラプソディ・イン・ブルー』末延芳晴)

全3幕9場、およそ3時間のオペラ『ポーギーとベス』が完成したのは1935年8月だった。作曲は全曲をジョージ・ガーシュウィンが、歌詞は原作者であるデュボース・ヘイワードと、ジョージの実兄で曲づくりの相棒であったアイラ・ガーシュウィンが担当している。ヘイワードとアイラは、正式の英語教育を受けていない、貧しい港町の黒人の英語で歌詞を書くことにこだわった。「Bess, You is My Woman, Now」や「I Loves You, Porgy」など、いくつかの曲のタイトルに文法の破格が見られるのはそのためである。
オペラのストーリーは原作にかなり忠実だが、原作に何度も出てくるコカイン吸引の場面は上演にケチがつくことを避けてか、あまり強調されていない。最大の違いはラストシーンである。原作はベスがチンピラの集団にさらわれ、ポーギーが一人なまず横丁に取り残される場面で終わるが、オペラではさらわれたベスをポーギーが舟で追いかけていくストーリーに変えられている。これによって物語の悲劇的な印象は薄らぎ、最後の曲である「Oh Lawd, I’m On My Way/おお主よ、私は祈りの道を」(この「Lawd」も正しいスペルは「Lord」である)の軽快な曲調が観る者にハッピーエンドを予感させる。
ガーシュウィン作『ポーギーとベス』の初演が行われたのは35年9月、会場はボストンの〈コロニアル劇場〉だった。出演者は原作どおり一部を除いてすべて黒人だったが、これは当時のエンターテインメント界においてはかなり異例のことであった。黒人の登場人物を白人に演じさせる選択肢もあった中で、黒人俳優の起用を強硬に主張したのはガーシュウィン自身である。
作品の評価は大きく分かれたようだ。好意的な評もあった一方で、デューク・エリントンは、黒人の生活や音楽伝統を正確に表現していない「黒塗りのメロドラマ」と批判した。エリントンがこの作品を絶賛するようになったのは、50年代に再演されてからである。

初演の時点で『ポーギーとベス』は正統なオペラとは認められずミュージカルとして扱われていたが、公演回数計124回というのはミュージカルとしてもかなり少ない数である。この作品がオペラ作品として認められたのは、ようやく1985年になってからだった。その年の2月、「オペラ界のエベレスト」と言われるメトロポリタン歌劇場で上演されたことで、「ユダヤ人がつくった黒人オペラ」は初演から半世紀の時を経て歌劇の歴史に名を刻むことになったのである。
当初は評価の低かった『ポーギーとベス』が、それでも忘れられた作品とならなかったのは、オペラ中の楽曲を多くのジャズ・ミュージシャンが取り上げたからだ。嚆矢となったのは、初演翌年の1936年7月にビリー・ホリデイが録音した「サマータイム」だった。黒人霊歌「時には母のない子のように」の旋律を参考にしてつくられたこの曲は、その後も数多くのミュージシャンにレコーディングされ、スタンダード・ソングとしての地位を不動のものとした。ほかにも、「愛するポーギー」「イット・エイント・ネセサリリー・ソー」「マイ・マンズ・ゴーン・ナウ」といったジャズ・スタンダードが『ポーギーとベス』から生まれている。
ジャズ・ミュージシャンが『ポーギーとベス』の楽曲集に盛んに取り組むようになったのは、このオペラが50年代に再演されてからである。メル・トーメ、ジョニー・ハートマン、デューク・エリントン・オーケストラなどによってほぼ全曲が録音された「完全版」や、エラ・フィッツジェラルドとルイ・アームストロングによるデュエット盤のほか、オスカー・ピーターソン、ハンク・ジョーンズ、モダン・ジャズ・カルテット、レイ・チャールズ、秋吉敏子らが『ポーギーとベス』を題材にしたアルバムをリリースしている。中でも、マイルス・デイヴィスとギル・エヴァンスによる1958年のアルバムが特別なのは、オペラのストーリーにとらわれず、かつ独自の要素を加えることで、『ポーギーとベス』をまったく新しい作品に生まれ変わらせているからである。
そのアルバムが生まれた経緯を掘り下げる前に、ギル・エヴァンスに関する「ユダヤ人問題」をはっきりさせておきたい。
ジャズ研究家のステファニー・スタイン・クリーズが著したギル・エヴァンスの評伝『Gil Evans Out of the Cool』(未邦訳)によれば、ギルの両親に関して知られていることはわずかである。ギルの母マーガレット・ジュリア・マコナキーはイギリス英語を話すスコッチ・アイリッシュで、ギルの父はカナダ人の医師だった。マーガレットは5回結婚しており、ギルの実父は4人目の夫だったようだ。その実父はギルが生まれる前に死亡し、マーガレットはカナダ人の炭鉱夫ジョン・A・エヴァンスと結婚した。ギルはその継父の姓を生涯名乗ったのだった。
『Out of the Cool』におけるギルの生誕と両親に関する記述は1ページ程度だが、日本語で読めるギルの評伝『ギル・エヴァンス 音楽的生涯』(ローラン・キュニー著)の言及はさらに少なく、わずか6行に過ぎない。書くべき情報に乏しいためだと思われる。いずれの本にもギルがユダヤ人であることを示す記述が皆無なのは、要するに彼がユダヤ人ではないからだろう。どうやら、ビル・エヴァンス同様、ギル・エヴァンスがユダヤ人であるという説明も、日本のみで通用する俗説らしい。
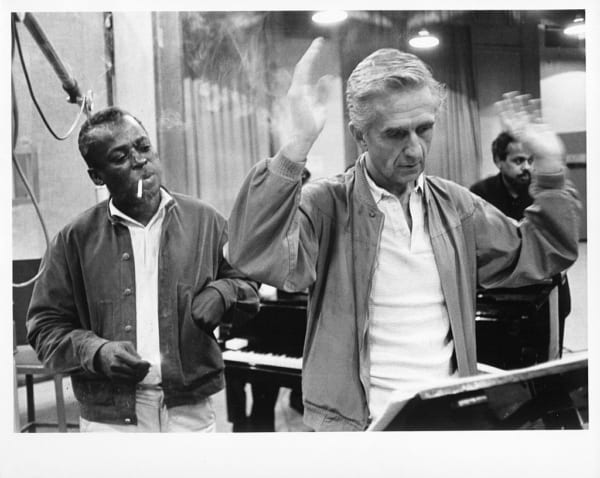
さて、マイルスはなぜ『ポーギーとベス』をレコーディングしようと考えたのだろうか。定評ある評伝『マイルス・デイヴィスの生涯』(ジョン・スウェッド著)によれば、最初にこの作品をギル・エヴァンスのアレンジでレコーディングすることをマイルスに提案したのは、コロンビア・レコードのカルヴィン・ランプリーだった。黒人として初めて白人アーティストを担当したことで知られるプロデューサーである。
マイルスは当初その話に乗らなかったようだ。その頃舞台で再演されていた『ポーギーとベス』は黒人団体から抗議を受けていて、この作品に関わることは得策ではないと考えたのだろう。作品に差別的な内容があったわけではない。たんに黒人の世界を白人が描いたことが気に入らなかったがための抗議だった。
しかし、盟友にして卓越したアレンジャーであるギル・エヴァンスとともにオペラという素材を料理することへの興味には抗し難かったのか、マイルスはランプリーの提案をほどなく受け入れた。そうして、1949-50年の『クールの誕生』、57年の『マイルス・アヘッド』に続くギルとのコラボレーション・プロジェクトがスタートしたのだった。
前年にレコーディングされたエラ&ルイによる『ポーギーとベス』は、オペラの展開に沿って曲をセレクトしてストーリーを尊重した構成になっていたが、ギルは曲順を変えるだけでなく、それぞれの曲のハーモニーを変更し、新しい旋律を加え、さらに書き下ろしのオリジナル曲を追加することで独立したジャズ・アルバムにすることを目指した。
2人がつくろうとしていたのは、ボーカルのないインストルメンタル・バージョンの『ポーギーとベス』である。しかし、彼らがあくまでこだわったのは「歌」だった。ギルは言っている。
この作品は『歌』なんだよ。だがマイルスは挑戦に応じた。『歌』を演ろうじゃないかってね。(『ギル・エヴァンス音楽的生涯』)
挑戦は簡単ではなかったようだ。中山康樹がマイルスにインタビューした際、「今まで一番苦労したレコードは」との問いに対して彼は『ポーギーとベス』と即座に答えたという。「“ベス、ユー・イズ・マイ・ウーマン”っていうセリフを8回も意味を変えて吹き分けなきゃならなかったからだ」というのがその理由だ(『マイルスを聴け!!』)。「歌う」ことに悩んだマイルスが手本にしたのは、フランク・シナトラやロバータ・フラックのボーカルのフレージングだった。手本にされた方のロバータ・フラックは、『ポーギーとベス』を初めて聴いたとき、マイルスが「言葉を演奏している」ことがすぐにわかったと語っている(『マイルス・デイヴィスの生涯』)。

レコーディングは、人間の声に近いサウンドを作り出さなきゃならないパートがいくつかあったりして、とても楽しかった。難しかったが、なんとかこなせた。ギルのアレンジは最高にすばらしかった。〈アイ・ラブズ・ユー・ポーギー〉のアレンジにはコードがなく、オレが演奏する音階だけが書かれていた。ギルは、それに基づくオレの演奏を、コードを二つだけ使ったその他の楽器のボイシングに当てはめた。それによって、多くの自由と、細部までよく聴き取れる空間を作りだすことに成功したんだ。(『完本マイルス・デイビス自叙伝』)
この発言の中で、マイルスははからずもジャズの歴史に関わる重要な事実を語っている。「愛するポーギー」の譜面にはコードの記載がなく、音階だけが書かれていた。ということはすなわち、『ポーギーとベス』の中の少なくとも1曲は、60年代に主流になるモード奏法に基づいて演奏されたということだ。
細かなコード・チェンジの束縛を脱して、特定の音階(モード)をもとに自由に即興を行うスタイルがモード奏法で、1959年にレコーディングされたマイルスの『カインド・オブ・ブルー』によってモード・ジャズは完成した──。こう説明すればジャズ史の教科書的解説となるが、実際にはその9カ月前にレコーディングされた『ポーギーとベス』にすでにモード奏法が導入されていたことをマイルスの発言は示している。1970年にジャズのエレクトリック化への道を本格的に拓いた『ビッチェズ・ブリュー』が発売されるまで、『ポーギーとベス』はマイルスの全リーダー・アルバム中最も多くのセールスを記録したレコードだったが、どうやらこのアルバムはたんに売れただけではなく、モダン・ジャズの新しい時代を拓く画期的な作品でもあったらしい。
マイルス版『ポーギーとベス』はクレジット上マイルスの単独リーダー作となっているが、実質的な作者はマイルスとギル・エヴァンスの2人であった。しかしギルは、このアルバムは「3人の共同作業」によって成立したものであると生前に語っている。3人とは、マイルスとギル、そしてジョージ・ガーシュウィンである。
もちろんガーシュウィンはこのアルバムに直接関わってはいないし、完成したアルバムを聴くこともなかった。彼はこのアルバムがレコーディングされる20年以上前の1937年に脳腫瘍で死んでいる。『ポーギーとベス』のスコアを仕上げてからわずか2年後。38歳での早逝であった。
さまざまな異人種からなるアメリカ社会を形容する「人種の坩堝(るつぼ)」という表現は、ユダヤ系英国人の作家イズレイル・ザングウィルの戯曲『坩堝(The melting pot)』に発するとされる。しかし、坩堝が異なる金属を高熱で溶かし混ぜ合わせて一体化させる容器の意であることを考えれば、「人種の坩堝」という言い方は極めて不正確と言うべきである。異なる人種や民族が完全に混ざり合うことはないからだ。アメリカ社会にあって異人種、異民族の間には常に大きな溝があったのだし、今もその溝はなくなっていない。
しかし、音楽にならば坩堝がありうるだろう。異なる土地、異なる文化、異なる人種、異なる民族から生まれた音楽が混じり合い一体化する坩堝が。ジョージ・ガーシュウィンは、自分の作品をそんな坩堝にしたいと願ったのではなかったか。黒人、ユダヤ人、その他もろもろの人種・民族の歴史と文化が混ざり合い、溶け合い、調和する。「ラプソディ・イン・ブルー」や『ポーギーとベス』でガーシュウィンが表現しようとしたのはそんな音楽ではなかったか。彼が短い生涯の中でつくり上げた「音楽の坩堝」。それはまた、ジャズという音楽の本質でもあるだろう。
(次回、最終回に続く)
〈参考文献〉『ポギーとベス』デュ・ボース・ヘイワード著/齋藤數衛訳(東京ライフ社)、『ギル・エヴァンス 音楽的生涯』ローラン・キュニー著/中条省平訳(径書房)、『Gil Evans Out of the Cool』Stephanie Stein Crease(Chicago Review Press)、『ラプソディ・イン・ブルー──ガーシュウィンとジャズ精神の行方』末延芳晴著(平凡社)、「ユリイカ」1981年12月号(青土社)『マイルス・デイヴィスの生涯』ジョン・スウェッド著/丸山京子訳(シンコーミュージック・エンタテイメント)、『マイルスを聴け』中山康樹(径書房)、『完本マイルス・デイビス自叙伝』マイルス・デイビス、クインシー・トループ著/中山康樹訳(宝島社)

3人のユダヤ人と「最高のジャズ・シンガー」が生み出した名曲─ビリー・ホリデイと「奇妙な果実」【ヒップの誕生】最終回
投稿日 : 2023.05.02 更新日 : 2023.06.20

ユダヤ人が書いた黒人オペラ ─『ポーギーとベス』に表現された「音楽のるつぼ」【ヒップの誕生】Vol.47
投稿日 : 2023.04.04 更新日 : 2023.06.19

「黒人性」と「ユダヤ性」のハイブリッド・ミュージック──「ラプソディ・イン・ブルー」が表現したアメリカの姿【ヒップの誕生】Vol.46
投稿日 : 2023.03.07 更新日 : 2023.06.16

「スウィングの王」と「史上最強のジャズ・レーベル」のオーナー ─ジャズの歴史をつくったユダヤ人たち【ヒップの誕生】Vol.45
投稿日 : 2023.02.07 更新日 : 2023.06.14