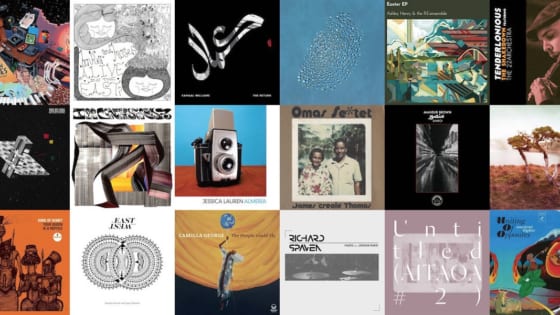投稿日 : 2019.08.13 更新日 : 2021.06.28
UKジャズの新ヒーロー、シャバカ・ハッチングスが語った “吹奏の奥義”【ザ・コメット・イズ・カミング|インタビュー】
取材・文/原 雅明 写真/平野 明

MENU
近年、南ロンドンを中心とした「UKジャズの興隆」が注目されている。なかでも、サックス奏者のシャバカ・ハッチングスは、もっともシンボリックな存在。そんな彼と、ドラマーのマックス・ハレット、キーボード奏者のダン・リーヴァーズによるトリオが、ザ・コメット・イズ・カミング(The Comet Is Coming)である。彼らは今夏、初来日しフジロックに出演。そのステージで見せたパフォーマンスは、どうやら大きなインパクトを残したようで、現場にはいなかった自分にも、関係者やオーディエンスから興奮ぎみの反応が伝わってきた。
●フジロックの前月、英グラストンベリー・フェスティバル出演時(2019年6月28日)のザ・コメット・イズ・カミング
シャバカが在籍する2つのバンド
ザ・コメット・イズ・カミングは、イギリスのインディ・レーベル〈リーフ(Leaf)〉 から発表したアルバム『チャンネル・ザ・スピリッツ』(2016年)でデビュー。次作『トラスト・イン・ザ・ライフフォース・オブ・ザ・ディープ・ミステリー』(2019年)は、60〜70年代のジャズファンを虜にした〈インパルス! レコード〉からのリリースを勝ち取った。

メンバーのシャバカ・ハッチングスは、自身が参加するもうひとつのグループ「サンズ・オブ・ケメット」でも、ひと足早く〈インパルス! レコード〉と契約し、アルバム『ユア・クイーン・イズ・ア・レプタイル』(2018年)をリリースしているが、両グループのサウンドは対照的だ。サンズ・オブ・ケメットはオーガニックで、トランス・カルチュラルな音楽としてジャズに向かっている。これに対して、ザ・コメット・イズ・カミングはUKのベース・ミュージックからインプロヴァイズド・ミュージック、サン・ラーやLAのビート・ミュージックまでを、改めてミュージシャンの視点から捉えて演奏している。

これは、フジロックに向かう直前におこなったインタビューだ。限られた時間だったが、彼らの音楽が、ロンドンのコミュニティとネットワークから生まれてきたこと、そして、綿々と受け継がれてきた背景があったことを伺い知れた。それは、いま音楽が成立する理由を改めて考えさせる話でもあった。
3人で「どこへ行けるか」を探求
──マックスとダンは「サッカー96」というユニットで活動していて、これにシャバカが加わり、ザ・コメット・イズ・カミングがスタートしました。そのときのことを教えてください。
マックス サッカー96として活動を始めたのは2009年だけど、僕らはその前から一緒にやってた。もともとは、独自にマイクのセッティングやレコーディング・プロセスなどのスタジオ技術を探求したいというところから始まったんだ。変わったロケーションで録音、演奏するとかね。そういうフリーなコラボレーションを作曲や録音でやってきたので、シャバカに出会ったときには、もうメソッドは出来上がっていた。彼が入ることで、このメソッドを使って即興的にさらに「どこへ行けるか?」を探求しようと思ったんだ。

──シャバカは、ふたりと一緒にやることに、どんな可能性を見い出したのですか?
シャバカ まさに「トラスト・イン・ザ・ライフフォース・オブ・ザ・ディープ・ミステリー」。このアルバムのタイトル通りだよ。この二人がステージでやってること、オーディエンスも含めて作り上げている生命力、エネルギーに無限大の可能性を感じた。そこに自分のエネルギーを加えたらどうなるだろう? それはミステリーといえるくらいに深いものになる予感があった。実際、やってみたらすぐにそれは正しいと感じ、ミステリーではなくなってしまったけど(笑)、すぐにまた新たなミステリーが生まれたんだ。
ダン スタジオで音を出した瞬間に「これは爆発的に素晴らしいものになる」と分かった。シャバカは即興で演奏してたんだけど、まるで、あらかじめ作曲されたものを演奏するみたいにメロディアスに吹いたんだ。

──シャバカはなぜ、そんなふうに吹ける?
シャバカ 音楽は統一性が重要だ。しかしジャズの場合、そうでなくていい部分もある。これはコートニー・パイン(注1)も言っていたけど、人は “基本的なこと”しか聴いていないし、理解もできない。音が大きいか小さいか、早いか遅いか、せいぜいそれくらいのことだ。それ以外のことは、ミュージシャンの自己満足であったり、専門家だけが詳しく知りたがるような要素なんだ。だから、多くの人が共通して「良い」と思えるものを追求しないといけない。つまり、メロディを弾くにしても、ただ練習して早く弾くのではなくて、言葉と同じくらい、はっきり語っていることが分かってもらえるように、言う(奏でる)ことが大切だ。それは僕だけでなく、3人が同時にやっていることなんだけど、そのなかで、いかに音楽を複雑化することなく、言いたいことをはっきり発音できるか。そこが重要なんだ。
注1:1964年ロンドン生まれ。サックスを主体に、フルートやクラリネット、キーボードも操るマルチプレイヤー。1986年にデビューアルバム発表。同年、ジャズ・ウォーリアーズ設立。大英帝国勲章のほか、ウェストミンスター大学やサウサンプトン大学の名誉博士号を授与されている。

──アルバムでは、たとえばシャバカの吹くバス・クラリネットとダンのシンセサイザーの音色が、じつにスムーズなレイヤーを作っているのが印象的でした。こうした、エレクトロニックなサウンドと一緒に演奏するとき、気に留めていることはありますか?
シャバカ それはスタジオを出たあとのポスト・プロダクションのおかげだと思う。あとシーケンスのバランスの良さはダディ・ケヴ(注2)も褒めていたよ。ここまで良いバランスのものは聴いたことがないと。
注2:エンジニア、プロデューサー、DJ。フライング・ロータスを筆頭にした“LAのビート・ミュージック”を牽引。特にそのマスタリング技術は、インストゥルメンタルのビートのみならず、カマシ・ワシントンらLAジャズの現場でも評価が高い。
ダン 僕はLAのビート・シーンにもっとも影響を受けてきたから、ケヴにマスタリングを頼むことが夢だった。インパルス!(レーベル)と契約できたときに「これはようやく頼めるな」と思って(笑)、何度も電話をかけたよ。最終的には音を聴いてもらって、やってもらえることになったんだ。
相互に響きあう「LAとロンドン」
──ケヴが主宰したパーティ「ロウ・エンド・セオリー(Low End Theory)」から登場したLAのビート・ミュージックは、UKのベース・ミュージックからも影響を受けてましたね。
マックス 僕はドラマーとして、LAのビート・シーンが持つ流動的なアプローチ、特に “リズムをグリッドにはめない” という考え方にすごく影響を受けた。リズムを会話的に捉えること、シンガーやラッパーのように捉えること、それが脈々と流れていると思うんだ。自分たちは真逆で、ライブでまずやる。それから、いかにテクニカルなものにプロデュースするか。例えば「Nano」(注3)や「Birth Of Creation」(注4)も、ドラムじゃない音に聞こえると思う。だからある意味、LAの鏡に映ったものをやっている感じだね。
注3:アルバム『チャンネル・ザ・スピリッツ』(2016年)収録曲。
注4:アルバム『トラスト・イン・ザ・ライフフォース・オブ・ザ・ディープ・ミステリー』(2019年)収録曲。
──なるほど。J・ディラ以降の「どうグリッドにはめないでビートを作っていくか」というアプローチは、LAもロンドンも、違う入口から同じところにアプローチをしている、とも言えますね。
シャバカ いまのジャズではプロダクションの部分がすごく重視されているよね。特に80年代のジャズは “演奏は素晴らしいんだけどプロダクションが酷い” というものが多かった(笑)。それはテクノロジーに洗練を求めるというより、単純に「新しいものだから使っている」というだけだったから。

シャバカ でも、いまはテクノロジーに対するプロデューサーの考え方も変わってきて、たとえば、カマシ・ワシントンとか、クリスチャン・スコットやポーラー・ベアとかもそうだけど、ソリストはソロを執って、その他のプレイヤーたちはあくまでプロダクションの一部で、「それを使ってどうやってサウンドを作り上げるか」ってところに観点が移っているんじゃないかな。
──あと、現在のジャズでは、バンドの背景にあるコレクティブやコミュニティの存在を感じることが多々あります。まさにあなたたちがそうですが。
ダン 音楽は多くの人と交わって、エネルギーを交換して、みんなで大きくしていくものだと思っている。そのハブになっているのが、僕らの場合はトータル・リフレッシュメント・センター(注5)だ。
注5:2012年の設立以来、ロンドンのジャズとクラブ・ミュージック・シーンの育成に中心的な役割を果たしてきたコミュニティ・ハブ。ライヴ等の多目的スペースの他、レコーディングやリハーサルのスタジオも併設する。
──それは、近年の“UKジャズの情勢”を語る上で、重要なコミュニティですね。
ダン あそこでいろんな人々と出会い、ジャンルを超えたプロジェクトがおこなわれ、次のことをみんなで計画しあったりした。そして、みんなで大きくなっていったんだ。でも、決してみんなが同じことをやっているわけではなくて、それぞれが違うことをやるのが推奨されてきた。自分たちで自分たちを発見しながら、お互いを受け入れあっている。互いの多様性に信頼を置きながら、みんなで団結しているんだ。だから僕らのアルバムも、ものすごく大きなコミュニティやネットワークから出てきたもの。その中のひとつに過ぎないと思っているよ。

──シャバカが関係していたトゥモローズ・ウォリアーズも、そういうものだったのですか?
シャバカ それはまた違うんだ。トゥモローズ・ウォリアーズ(注6)は若い人たちが学び、機会を与えられるプロジェクトが必要で生まれたものだね。トータル・リフレッシュメント・センターはもっと自然発生的に生まれたコミュニティだった。
注6:若手ミュージシャンの育成を目的とした組織。ベーシストのゲイリー・クロスビーが1991年に設立。ゲイリーはジャズ・ウォーリアーズ(コートニー・パインやクリーヴランド・ワトキスらが在籍したグループ)のメンバーとしても活躍した。
「考える」のは、あとでいい。
──僕はマックスのお母さんであるシルヴィア・ハレット(注7)や、UKのユニークなインプロバイザーの音楽も好きなのですが、その世界はあなたにとってどういうものでしたか?
マックス 父(クライヴ・ベル)もフリー・インプロバイザーで、一時期は日本に住んで尺八を学び、それで即興演奏もしてたんだ。だから、自分にとって子供の頃からジャズはずっとフリー・ジャズで。サックスなんかとても過激に吹かれたものばかりを聴いていた。落ち着いたジャズを初めて聴いたのは随分あとになってからで、逆にビックリしたよ(笑)。両親は、僕の音楽活動に関してもすごくサポートしてくれた。
注7:インプロバイザー/作曲家。エヴァン・パーカーやデヴィッド・トゥープらとともに、ロンドンのフリー・ミュージック・シーンを形成した一人。バイオリンやエレクトロニクスから、自転車のホイールやのこぎりなども使ったパフォーマンスや録音を70年代からおこなっている。
──具体的に学んだことは?
マックス 「実験精神を持て」と言われてきたよ。あと、遊び心も忘れるな、あまり真面目にやるな、ともね。80年代、ちょうど両親がいまの僕くらいの年齢のとき、ある音楽組織の委員を務めていたんだ。それはロンドン・ミュージシャンズ・コレクティブというフリー・インプロビゼーションを中心にした自主組織で、アイディアとしてそれに近いものを、いまトータル・リフレッシュメント・センターでおこなわれていることにも感じるんだ。

──ザ・コメット・イズ・カミングはサン・ラ(注8)からの影響を表明してますね。シャバカはマーシャル・アレン率いるサン・ラ・アーケストラにも参加してましたが、そこで得たものは?
シャバカ 演奏の休憩中、マーシャル・アレンにこう言われたよ。「きみはいまプレイしながら考えてたね。それが聞こえた。間違っているかどうかを考えながらプレイするのではなくて、ただその瞬間をプレイしろ。考えるのはあとでいい」。それが学んだことのひとつ。あと、アーケストラ自体が大きな有機体というか、家族なんだけど、必ずしもハッピーな家族ではなく、家族ゆえのいろんなしがらみもある。それを含めた上での家族なんだ。感情的なことも、良いことも悪いことも含めて、壊れているんだけど繋がっている。そんな感覚だったよ。
注8:米アラバマ州出身の音楽家(1914-1993)。独自の“宇宙的”哲学に基づいた音楽活動を実践。50年代に結成されたサン・ラ・アーケストラは、彼の死後もサックス奏者マーシャル・アレンらによって活動が続けられている。
──今日、あなたたちの話を伺って、なぜいまロンドンから登場するジャズが多様性を持っているのか、よく分かりました。
ダン ミュージシャンによっては、ずっと “ジョン・コルトレーンのふり” をしたい人もいる。いまだにビートルズのふりをしている人もいる。そういうトラディショナルなものを好む人もいれば、もっと新しいものを作りたい、自分の中にあるものを表現したいという欲望を持っている人もいる。少なくとも、自分は後者だ。自分がいままで影響を受けてきたいろんな音楽や、社会に対して「返せること」として、そうしたい。きっと、そういう人が僕らの周りにも集まっているんじゃないかな。